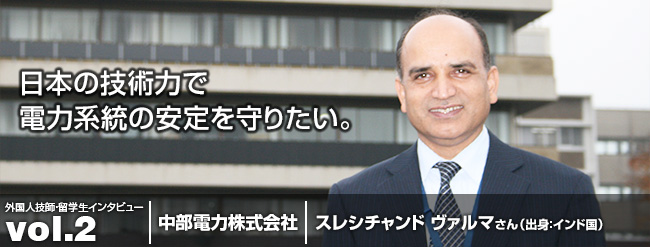vol.2 中部電力株式会社
2013年3月18日掲載
スレシチャンド ヴァルマさんは、中部電力株式会社で電力系統のご研究をされています。本国インドでは、大学院で電気工学の制御の研究をされた後に、電力会社に就職したヴァルマさんは、あるきっかけで日本に留学し、そのまま日本に就職されました。電気のどこに魅力を感じたのか、またなぜ日本へ留学されたのか、日本で就職を決めた理由などをお聞きしました。聞き手は北海道大学の北裕幸教授です(第一回目の三菱電機株式会社もご担当)。
プロフィール
- 1981年
- パンジャブ大学 電気工学部工学部電気工学科卒業
- 1986年
- ルールキー 大学(現在の工科大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了。
インドでは電力会社等に勤務 - 1990年
- 来日。
- 1991年3月
- 名古屋大学 日本語コース(6ヶ月間)修了
- 1994年3月
- 名古屋工業大学大学院工学研究科電気工学専攻博士課程修了。博士(工学)
- 1994年4月
- 中部電力(株)入社
現在、同社電力技術研究所に所属。主として、電力系統の解析・制御等に関する研究業務に従事 - 現在
- 同社電力技術研究所に所属。主として、電力系統の解析・制御等に関する研究業務に従事
- 2003年
- 電気学会論文賞受賞。IEEJ上級会員、IEEE会員
※2012年11月現在。本文中の敬称は略させていただきました。
インドの大学での電気工学の研究について

インドの大学で電気工学を学ばれていますが、そのきっかけは何でしょうか?
ヴァルマ:電気はわれわれの生活をはじめ、企業・インフラ・病院など重要な設備に欠かせないエネルギーであり、その技術にとても魅力を感じていました。子供のころから勉強したいと思っていました。
インドの大学ではどのような研究をされていましたか。
ヴァルマ:私はパンジャブ大学の電気工学部を卒業し、その後インドの企業にしばらく勤務してから、ルールキー大学(現在のインド工科大学)の大学院修士課程に進みました。大学院では、マイクロプロセッサーを使った水力発電所を制御する研究を行っていました。その当時は大型コンピューターではなく、出たばかりのインテル8085というマイクロプロセッサーの入った小さなコンピューターで、アセンブリ言語(プログラミングする言語)で組んで電気の周波数や電圧を測定したり、発電所の同期装置などのプロトタイプを作ったりしていました。
マイクロプロセッサーを使った発電所の制御とは?
ヴァルマ:水力発電所の起動停止の操作を手動ではなく、コンピューターが自動で操作するという研究です。具体的には、発電機を起動させて電力系統に並列させる同期装置についての研究です。
同期装置とは何ですか?
ヴァルマ:発電機を電力系統に並列させるには、発電機の電圧・周波数・位相を、電力系統の値にそれぞれ合わせる必要があります。一般に発電機の位相と電力系統の位相には差があり、まず双方の電圧を合わせ、発電機の周波数を系統周波数より少し高くして、位相が合った瞬間に発電機遮断器を投入して系統に並列させます。これを同期投入と言い、人間が手動で経験的に行っています。そこでコンピューターを用いて自動で系統に並列させる同期投入装置を作っていました。
コンピューターを活用することで同期投入の操作が飛躍的に向上したのですね。
ヴァルマ:はい。スムーズな同期投入は発電機のショックを減らし、発電機の寿命を長くすると考えられます。この研究を通して、人間が手動で行っている電力系統の様々な問題に対して、コンピューターを活用して自動で行ない、きめ細かく制御する技術にはとても魅力を感じるようになりました。
大学院卒業後はインドの電力会社に約7年間お勤めされましたが、インドの電力系統の特徴を少し教えてください。
ヴァルマ:インドでも、電気の重要性が高まっており、現在、電力のピーク時期には、約10%の電力が不足します。このため政府は多くの発電所建設を進めています。発電の種別では、火力と水力の比率がおよそ7:2ですが、再生可能エネルギーと原子力の割合が少しずつ増えています。また、以前の電力会社は発電から送配電まで垂直統合された一体の電力会社でしたが、10年くらい前から自由化が進み、州によっては、かなり発送電分離が進んでいます。また、大きな「パワーグリッド」という国全体の系統を管理・運用する送電会社(Power Grid Corporation of India Limited)ができて、全体の運用を行っています。
来日時、日本語は「さよなら」しか知りませんでした
<日本への留学について>

日本への留学を決めたきっかけは何ですか?
ヴァルマ:ある時、新聞に日本の文部省(現在の文部科学省)とインド政府との間で「マイクロプロセッサー」というテーマ付きの奨学金の募集がありました。私は大学院時代にマイクロプロセッサーを研究し、インドの電力会社でもマイクロプロセッサーを使ったプロジェクトをやっていたので、この奨学金に応募しようと思ったのがきっかけです。具体的な大学は文部省の方で探してもらいました。
日本以外の国に留学しようという気持ちはなかったですか
ヴァルマ:マイクロプロセッサーを生かした研究を海外で行いたいという気持ちがあった中で、日本の技術は世界の中でも特に優れているイメージがあり、チャンスがあれば是非行きたいと思っていました。同僚や上司の勧めもあって日本に行くことに決めました。
日本語はどうでしたか?
ヴァルマ:日本に来たときは「さよなら」しか分かりませんでした。インドの大学の講義は全部英語で行うので、英語が普通にできると思われていたようですが、日本では私の発音が悪いのか、なかなか通じませんでした。6か月間、名古屋大学で日本語の勉強をして、何とか話せるようになりましたが、相手の話を聞き取ることは5~6割くらいでした。特に、「ちょっと」という言葉がわかりづらかったですね。外国人からすると、ちょっとはYesなのかNoなのかはっきりしません。日本人はこれだけで話ができるので、すごいと思いましたね。
今は日本語がとっても上手ですよね。
ヴァルマ:オンライン辞書があって読み方も意味も分かるのでとても便利です。日本語で書かれている文章は電気関係であればほとんど問題なく読むことができます。実は、7月1日からチームリーダーになり管理業務が主体となって、研究の立案などは文章を書いたり読んだりする仕事がほとんどです。
日本の食べ物はどうでしたか?
ヴァルマ:最初は醤油の独特な匂いがだめで苦労しました。日本に初めて来た時に、醤油の匂いを強く感じました。今は全然気になりませんが。
名古屋工大・中村研究室で新型プロセッサーの研究を行う
日本の大学院での研究は?
ヴァルマ:日本では、名古屋工業大学の中村光一先生の研究室に入りました。マイクロプロセッサーを使った発電機の制御について先生に提案したのですが、日本では発電機制御の研究はかなり進んでいると言われました。そこで、名古屋工業大学の研究室ではDSP(Digital Signal Processor)という新型プロセッサーを電力系統の運用に生かす研究を行っており、私もその適用方法とその特徴に合った計算方法について研究しようと考えました。
大学の研究室での思い出は何かありますか?
ヴァルマ:先生は厳しい方で、研究室にはいつも学生がいて一生懸命研究していましたね。ゼミを必ず2~3週間に1回行っていて、きちっとできていないと相当怒られました。今の先生と比べて厳しいと思いますよ。
日本に来て3年間で博士論文をまとめて修了されたのは、すごいですね。やはり研究面では相当苦労しましたか?

ヴァルマ:そうですね。ただ、インドの修士課程の時の研究が非常に役に立ったと思います。それと、先生からその時の研究の状況について図書館でよく調べるように言われ、2か月間くらいかけてしっかり調査したのが良かったと思います。初めはなかなか成果が出ませんでしたし、データ構造も自分で作らなければなりませんでしたので、苦労しました。
日本企業で働いて真の技術力を身につけたい
日本に就職されたのは、なぜですか。
ヴァルマ:最初はインドに戻る予定でした。電力会社の仕事もありましたし。ただ、博士課程では基本的に大学内での研究だったので、日本企業の技術を本当に実感することはできませんでした。日本の魅力は企業にあり、企業ではいろいろな技術力を持っているはずだと思い、1~2年間、こちらの企業で働く経験をしたいと考えました。また、環境が非常に自分に合っていました。自由ですしメーカーや大学とも相談できる技術的なフローがありました。初めはインドに戻るつもりで、中部電力には契約社員で入りましたが、その後数年間勤めて、正社員として日本で研究を続けることになりました。
電機メーカーへの就職は考えなかったのですか?
ヴァルマ:先生の紹介でメーカーの研究所なども見学しましたが、インドで電力会社の仕事経験がありましたし、インドに戻るつもりだったので、名古屋工業大学と共同研究をやっていた中部電力に決めました。
中部電力は博士課程の学生を採用する制度はあったのですか。
ヴァルマ:研究所に専門研究員という制度があり、私もその制度で入りました。ずっと研究所の勤務になります。今は、多くの専門研究員が博士の学位を持っていますね。修士卒の研究員も、入社してから博士の学位をとる人が多いと思います。
留学生の採用はありますか?

ヴァルマ:研究所ではありませんが、国際事業部で中国からの留学生が働いています。
太陽光発電が大量導入されても、系統の安定性を維持する研究
<現在のお仕事について>
現在のお仕事は?
ヴァルマ:太陽光発電が電力系統に大量導入されても、系統安定性を維持できるようにする研究を行っています。
太陽光発電と電力系統の安定度はどのように関係するのでしょうか。
ヴァルマ:電力系統につながる多くの電源は、一般に電力系統内で何らかの擾乱が起こって系統の状態が大きく変化しても、それを元に戻そうとする力を持っています。この力を同期化力と言い、電力系統を安定的に維持しています。電力系統は需要と電源がバランスしていますが、太陽光発電が大量に導入されると、バランスさせるため、系統を維持するのに重要な回転型の電源を止める必要があります。同期化力のある電源が少なくなるため、雷で電源が停止したり、太陽に雲がかかって太陽光発電の出力が急変したりすると、電力系統の安定性が維持できなくなります。また、太陽光発電は、同期化力を持っておりませんので、系統内の擾乱に対して安定性を維持することが難しくなります。
今の仕事で、一番印象的なエピソードや楽しかったことは何ですか?
ヴァルマ:自分で開発したソフトを使って計算した結果と、現場で実測した結果がほとんど一致したので、計算でもかなりのことがわかるのだと実感したことです。また、現場の方が相談に来られて、リレーがトリップした原因が分からないので解析してほしいという依頼で解析した結果、需要家側の誘導機が、事故の発生後に故障電流を供給していることが分かりました。それまでは負荷が故障電流を供給するという概念がなかったので、解析によってその原因がわかったことはとてもうれしかったですね。今では、この解析結果がリレー整定などに活用されています。
学生時代の電気工学の研究は現在のお仕事にどのように生かされていますか
ヴァルマ:潮流計算を研究していたので、位相と系統の関係がすぐにイメージできます。位相という概念は難しいですが、このイメージはとても重要だと思います。今の学生さんはこの系統解析部分がブラックボックスになっていますね。これで仕事はある程度できますが、何かあった時にどうすれば良いのか分からないのではと懸念しています。
今振り返ってみて電気工学を学んでよかったことを教えてください。
ヴァルマ:最初に申し上げましたが電気はエネルギー的に重要な基盤エネルギーであり、クリーン、速い、運びやすい、制御しやすいなどの特徴を持っています。こういう技術に関われるのは今でもよかったと思っています。また、現在、私はオール電化住宅に住んでいますので、電気がなくなると大変困りますね。ただし、21年間名古屋に住んでいますが、一瞬でも停電になったことがありません。このぐらい日本の電気は供給信頼性が維持されていますね。これは電気が重要なエネルギーであるため、逆に供給信頼性を維持しなければならないのかもしれません。
日本に来て留学・就職して良かったと思うことは?
ヴァルマ:自分が今のような仕事ができるのは、自分だけでなく相手を尊重しながら協力してくれる日本の組織のおかげだと思っています。また、国内でも様々な先生方にお世話になって支えてもらっています。海外でも国際会議、CIGREなどの委員会でも委員にしていただき、いろいろな人に会えたのは、日本にいるおかげだと思います。
お仕事で今後どのようなことをやってみたいですか

ヴァルマ:今研究している太陽光発電の技術や、系統解析シミュレーターを開発していきたいと思います。系統を安定運用するというのは、環境がどのように変化しても重要なことなので、研究面でこれをしっかり支えていきたいと思います。それから、太陽光発電は配電系統に導入されるので、配電系統の電圧維持が難しくなります。今、新型電圧安定装置を研究しており、動作原理を確認しているところです。また、PMU(Phasor Measurement Unit)という時刻同期の測定が可能な装置を利用して系統特性や、系統運用限度の把握ができますので、これを監視制御技術に使っていくような安定化制御装置を作っていきたいと思っています。
インドから日本への留学についてアドバイスがあります
最後に日本への留学に興味のある学生さんに対して何かアドバイスはありますか
ヴァルマ:日本は、技術や文化の面で非常に教わることが多いと思います。日本の習慣を習うことは世界的にも役に立つことが多いと思います。日本は理想的な国と言っても過言ではないと思います。
どうすればもっと日本への留学生が多くなると思いますか。

ヴァルマ:インドでは大半がベジタリアンなので、食べ物がネックかなと思います。また、インド人は英語ができるので、留学先はアメリカやイギリスが多くなっています。このため奨学金などの面でメリットがあるとよいと思います。物価が高いイメージもあるので。金銭面が大事だと思います。日本では言語の面からアルバイトが難しいので、生活費の援助があると良いと思います。
ヴァルマさん、今日はどうも、ありがとうございました。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。