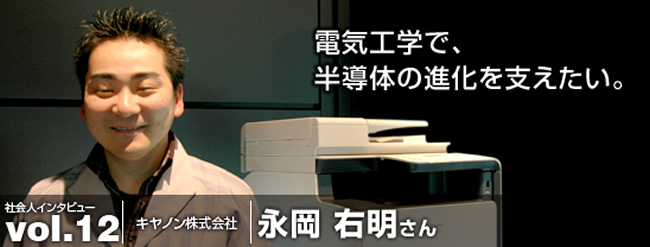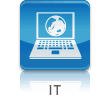vol.12 キヤノン株式会社
2011年4月22日掲載
キヤノン株式会社は、デジタルカメラやビデオカメラなどの映像機器、プリンターなどの事務機器等で、世界トップクラスのシェアを誇る、日本を代表する電気機器メーカーです。今回、インタビューを引き受けて頂いた永岡さんは、主にカラーレーザープリンターの半導体を開発する現役エンジニアです。
プロフィール
- 2004年
- 東京都立大学(現:首都大学東京)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程終了(安田研究室)
- 2004年
- キヤノン株式会社入社 NPC開発センターに配属
- 2008年
- SOC開発センターへ異動、業務内容は変化せず
- 2009年
- SOCデザインセンターに異動、ASIC開発における論理検証業務に従事、現在に至る
※2011年1月現在。文章中の敬称は略させて頂きました。
実は、文系科目が得意でした(!)

電気工学科へ進まれた理由を教えてください。
永岡:正直なところ、確固たる理由があったわけではないのです。ものづくりに興味があったので、工学部へ進みましたが、電気工学科は偏差値で選びました(苦笑)。
では、文系よりも理系が得意でしたか。
永岡:いや、どちらかというと、文系科目のほうが得意でした(笑)。父親が大学で文学を教えていて、その影響で小さなころから本ばかり読んでいましたね。 高校の先生からも「文系へ行ったら」と言われました。でも、元々理系には興味があったので進んだ感じです。物理はあまり得意ではありませんでしたが(苦笑)。
実際に大学へ入学されてみていかがでしたか。
永岡:大学へ入ってから、面白くなってきましたね。理系に来てよかったなと思ったのは、学部生のとき、人力飛行機研究会に所属して、テレビの「鳥人間コンテスト」に出る飛行機を作った時です。設計などを担当して、ものづくりに欠かせない理系科目が一気に好きになりました。
授業はどうでしたか。
永岡:確かに難しいところはありましたが、コンピューターをいじるようになってから、自然と好きになったと思います。特に、安田先生の授業が好きで、もっと深く研究したいと考えて院へ進みました。
システム最適化の研究に没頭した、学生時代

学生時代は、どのような研究をやられていましたか。
永岡:システム最適化手法のひとつの「メタヒューリスティクス」という研究です。システム最適化というのは、簡単に言いますと、一般的に難しいと思われる課題を解決するために、無限の組合せの中で最適なものを選ぶ研究です。"組合せ最適化"とも呼ばれます(※)。
(※)詳細は、学生インタビューVol.6/安田研究室をご覧ください。
メタヒューリスティクスとは何ですか。
永岡:システム最適化の中で、大規模な問題に対して、現実的な解を見つける方法が「メタヒューリスティクス」です。無限にある組み合わせの中から最適なものを選ぶ場合に、「これとこれを組み合わせたらいいものができるだろう」という、人間の経験的感覚を取り入れたアルゴリズムによって「解」を導き出します。
具体的にどのようなことに役立てることができますか。
永岡:私たち人間は、基本的に何か物事を決定するときには、無意識に又は意識的に、すべて最適なものを選択しようとします。ですから、この「メタヒューリスティクス」は社会生活すべてに役立つ研究です。具体的な例ですと、カーナビにおける最適な経路選択や、発電システムの需要量など、様々な事にこの最適化という研究を役立てることができます。
研究をされていて、印象に残っていることを教えてください。
永岡:大変だったことが一番印象に残っていますね(苦笑)。修士論文を書いていた時は、元日の1月1日から研究室へ行って、PCでシミュレーションをしていました。
では、研究室自体で思い出に残っていることはありますか。
永岡:毎年行っているゼミ合宿ですね。箱根や河口湖へ行って、温泉や景色などを楽しみました。そして、ゼミ発表で大激論を一晩中やりました。まさに「学生時代」しかできない経験をさせていただいたと思います。今、社会人になってからも、ゼミ合宿に呼んで頂いています。
エレクロニクス機器の頭脳、半導体をつくる

キヤノンへ入社された理由を教えてください。
永岡:キヤノンは技術を大事にしている会社というイメージがあったことです。私は、技術者として就職したいという思いがあったので、キヤノンへ進みました。
入社されてから、どのような仕事をやってこられましたか。
永岡:入社時はカラーレーザープリンター用ASICの設計及び検証業務両方を担当していましたが、現在はプリンターに限らず様々な製品に搭載されるASICの検証業務を専門に行っています。ASICとは、特定の用途向けにつくられた半導体(IC集積回路)のことです。半導体はよくコンピューターの頭脳と言われますが、簡単に言えば、ASICによってカラーレーザープリンターが正常に動くというわけです。
今のカラーレーザープリンターは、事実上コンピューターというわけですね。
永岡:はい。全部デジタル処理によって、プリントされています。また、画像処理だけでなく、プリンターの機械自体の動作も、ASICによるものです。プリンター全体をコントロールする頭脳と思ってもらって良いと思います。

永岡さんが手掛けたASICが搭載されている、カラーレーザープリンター
このASICはどのような流れでつくられているのですか。
永岡:非常に大雑把な説明になりますが、まず、仕様を決めます。次にその仕様に沿って、ハードウエア記述言語を用いてプログラミングなどを行い、デジタル回路を設計・開発します。出来上がった回路を検証者へ渡して、コンピュータ・シミュレーションでテストします。これを検証と言います。それから、チップ内部における回路の配置配線・電源・ノイズ等のアナログ回路的な部分での検討や対策を行った後に生産・量産へと移ります。
どれくらいの期間によって、作られるものなのですか。
永岡:チップの規模(情報量)によって、様々ですね。どれだけの情報を持っているかで、検証期間もまるで変わっていきます。
チップとなると、いわゆるナノテクノロジーと呼ばれることをやっているわけですね。
永岡:そうですね。チップの大きさ自体は、回路の規模にもよりますが数ミリ四方から数センチ単位のものまでいろいろあります。しかしながら、内部の回路の配線はナノメートル(nm:1メートルの10億分の1)単位のもので、そのチップ内部に膨大な情報量を埋めていく作業になります。
今の仕事をされていて、印象に残っているエピソードはありますか。
永岡:自分で設計したモジュールを組み込んだチップで、プリンターが初めて動いた時は良く覚えています。実際にプリンターから絵が出た瞬間は、身震いするほどうれしかったです。技術者の醍醐味ですね。
電気工学をやっていて本当に良かった!

学生時代に学んだ電気工学は、どのように今の仕事に活かされていますか。
永岡:今の仕事は、半導体関連なので、どちらかというと電子工学の世界です。ですから、電気工学やシステム最適化の研究とは直接、関係がありません。ただし、困難にぶつかったときの対処や解決方法などは、大学の研究室で多く学んだと思っています。日々、研究室の仲間達や先生方と議論を重ねながら研究に取り組んだことによって、様々な課題への対処方法が身についたと考えています。
基礎的な知識は活かされていませんか。
永岡:電気工学の基礎知識は、技術者にとっては共通言語のようなものです。特にデジタル回路やアナログ電気回路の知識は知らないと、メーカーの仕事は何もできないと思います。
電気工学を学んだ技術者は、他の学科出身と比べて、どの辺りが強みだと思われますか。
永岡:幅広くものづくりの知識が身につくことではないでしょうか。電気系技術者は、ソフトウェアからハードウェアまで幅広く関わることで、広い視野と見識が身につくと思います。私もお世辞抜きで「電気工学をやっていて本当に良かった」と、はっきり言えますね。
あらゆる分野で電気系の技術者は、求められています

最後に、これから後輩になる方々へ電気工学の魅力をお伝えください。
永岡:小さなことを言うと、ちょっとした電化製品の修理ができるようになりますね(笑)。大きなことを言うと、これからどんな分野でも電気系の技術者は求められるようになると思います。
具体的に教えてください。
永岡:私はここ数年リクルーティング活動のお手伝いもやっているので、毎年大学へ行く機会があるのですが、「電気系の技術者が必要である」ことが、今、すごく感じられます。今後、自動車にしてもエネルギーにしても、ほとんどが電気に関連しているので、ますます重要性が増してくる分野だと思います。極論を言えば「この分野をやりたい」と決まっていない人は、電気工学をやっておくと、後で選択の幅が広がるのではないでしょうか。
今、人材市場で電気系技術者は非常にニーズがあるというわけですね。
永岡:そうです。だから、電気系技術者は、どこへ行っても活躍できる人材だと個人的には考えています。例えば、営業やSEをやっている方も、実は電気工学の技術者だということが多く見受けられます。ぜひ電気工学を学んで、より良い人生の糧にしてほしいと思います。
本日は、現場で活躍されている技術者の生の声を伺えて大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

- 公立/東京都
- 首都大学東京 理工学研究科 電気電子工学専攻
安田 恵一郎 教授(やすだ けいいちろう)
当研究室では、システム工学(最適化と制御)とエネルギーシステム・電気機器への応用に関する研究を中心に行っています。1991年以来、80名を超える学部生・大学院生が当研究室で学び、さまざまな分野で活躍しています。本学は少人数教育のため、密度の濃い教育・研究環境が提供されています。2010年度は、スタッフ3名、博士前期課程5名、学部生3名の総勢11名で活発な研究活動を行っています。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。
バックナンバー
- vol.52 電気工学を活かして技術の発展に女性の視点を反映したい
- vol.51 東西日本間の電力融通を通じて安定した電力供給に貢献したい。
- vol.50 情報科学の知見を活かして電力業界のDX化に貢献したい。
- vol.49 電力業界の新たなルールへの対応の検討を通じ、カーボンニュートラルの実現に貢献したい。
- vol.48 変電技術者として変電所の運営に携わり、電気のある明るい生活を支えていきたい。
- vol.47 空港という重要施設を電気のスペシャリストとして守っていきたい
- vol.46 海底ケーブルのスペシャリストとして電力インフラを支えていきたい。
- vol.45 「ワクワクしつつ冷静に」をモットーに電力の安定供給に貢献したい。
- vol.44 “縁の下の力持ち”として測定器づくりによって社会を支えていきたい。
- vol.43 電力インフラを支える仕事を通じて、環境保護などの社会貢献を続けていきたい。
- vol.42 誰からも認められる女性技術者となり、 発展途上国の人々の暮らしに貢献したい。
- vol.41 電験1種取得者としての専門性を活かし、 電力業界で必要とされる人材であり続けたい。
- vol.40 電気工学の知識をもっと身につけ、 信頼される技術者になりたい。
- vol.39 大容量の電力貯蔵を実現するNAS電池の普及を通じてエネルギー問題の解決に貢献したい。
- vol.38 電気工学の知識を活かし、設備設計のプロとして活躍したい。
- vol.37 電動化が進むクルマの、これからの進歩を支えたい。
- vol.36 電力を支える使命を持った 信頼される存在になりたい。
- vol.35 世界に広がる活躍のステージ。 社会貢献への期待に応えたい。
- vol.34 四国の電力を支える使命を持って、火力発電の未来を拓きたい。
- vol.33 世界中のヒトに信頼される、建設機械を設計したい。
- vol.32 変電設備の最前線で、 電気の安定供給に尽くしたい。
- vol.31 都市レベルでものごとを考えられる、広い視野を持った電気設備設計者になりたい。
- vol.30 高電圧・高電界分野の技術開発で、 電力機器を進化させたい。
- vol.29 電力系統解析の研究者として、 社会や現場のニーズに応えたい。
- vol.28 電力・エネルギーの専門家として、社会に広く情報発信したい。
- vol.27 世界の海洋開発と海上物流を、最先端の電気技術で支えたい。
- vol.26 電力系統を守って人々の生活を支えたい。
- vol.25 新しい制御技術で、 環境にいいクルマを実現したい。
- vol.24 世界の産業を支える 技術者として活躍したい。
- vol.23 日本が誇る電力技術を、 世界に広めたい。
- vol.22 宇宙を駆ける、世界初のものづくりをしたい。
- vol.21 電気工学を活かして、交通安全を支えたい。
- vol.20 製鉄現場を電気技術者として支えたい。
- vol.19 エネルギー・環境問題の解決と、 日本の産業を強くしたい。
- vol.18 電力の安定供給を支えたい。
- vol.17 ものづくりの現場に、 電気の専門家として貢献したい。
- vol.16 社会の役に立つ、電気の研究をしたい。
- vol.15 電気工学で、地球環境を守りたい。
- vol.14 世界に広がる省エネ機器をつくりたい。
- vol.13 世界中の社会インフラを支えていきたい。
- vol.12 電気工学で、半導体の進化を支えたい。
- vol.11 電気工学で、日本の鉄道を支えたい。
- vol.10 世の中ではじめての電力機器をつくりたい
- vol.9 電気を広めて、紛争のない世界を実現したい。
- vol.8 宇宙空間で動く、究極の電源をつくりたい!
- vol.7 風力発電で、エコの輪を世界へ広めたい。
- vol.6 電気工学で、日本のケータイを世界へ広めたい。
- vol.5 夢の超電導ケーブルを、世界中で実現したい!住友電気工業株式会社 西村崇さん
- vol.4 エコキュートをもっと便利に。電気工学で地球環境を守る。
- vol.3 電気は、社会に不可欠なライフライン。だから、私は高電圧・大電流に向き合う。
- vol.2 電気工学を応用して、世界一のハイブリッドーカーを開発したい!
- vol.1 電気工学は一生の財産。どこへ行っても使える学問です。