vol.25 横浜国立大学
2013年10月31日掲載
横浜国立大学の大山力・辻隆男研究室では、「将来の電力・エネルギー供給のあり方を探る」をスローガンに掲げ、電力システムを取り巻く様々な問題を取り扱っています。近年は、分散型電源の増加など電力業界を取り巻く状況が大きく変わりつつあるため、最先端の電力システム研究は学会や産業界から注目されています。
※2013年9月現在。文章中の敬称は略させていただきました。
私たちに身近な存在だから深く学びたかった
みなさんが電気工学を志望された理由について教えてください。

秋山:父が電子情報工学科を卒業し、電子計測器のプログラミングの仕事をしていたことが、そもそものきっかけでした。学部時代、電気工学の大山先生の授業で日本の品質の高い電力供給を知り、この分野に関心を持つようになりました。
理系ということは最初から決めていましたか。
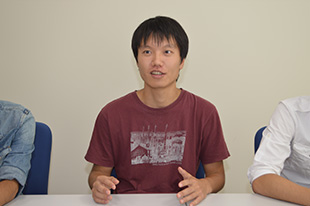
秋山:ええ、高校時代は文系より理系科目が得意だったので、はっきりと決めていました。
斎藤:私の場合、大学に入学した頃は、電気・通信・情報と幅広い分野に興味がありました。大学でこれらの授業を受けるうちに、我々の生活をあらゆる角度から支えているのが電気工学だと知り、深く学びたいと思うようになりました。やはり電気のフィールドが一番広く、魅力的でしたね。東日本大震災もインフラとしての電力の大切さを改めて見直す、きっかけになりました。
専門分野はどうやって絞りこんだのですか。
斎藤:はい。電気・通信・情報のいずれも身近な技術として自分たちの生活を支えていますから、どれも興味がありました。だから広く学んでいくうちに、絞っていったという感じでしたね。
塩原:私が電気工学を選んだのは、工学分野の中で最も格好いいと思ったからです。
なにが格好いいと思ったのですか。

塩原:私は高専の出身ですが、中学から高専に進むときに機械にしようか電気にしようか迷いました。正直に言うと、どちらでもよかったのですが(笑)。それで電気に入ったところ、これが予想以上に難しくて、最初の頃はすごく成績も悪かったのです。でも頑張って勉強しているうちに、こんなに難しい勉強をするのって格好いいなあ、と(笑)。それに電気というのは供給する地域によって固有の技術があり、そういうことを知るうちに将来は電力システムに携わりたいと思うようになりました。
高専卒ですと、大学3年生で編入されたわけですね。
塩原:ええ。北陸地方の出身ですので、せっかくなら首都圏の大学で学びたいと思いました。電力のダイナミックさを感じるには、やはり日本の中心である首都圏がいいと考えました。
本格的な再生可能エネルギーの時代を見据えて
みなさんは現在、どのような研究に取り組んでいらっしゃいますか。

秋山:これから電力制度改革が進み、日本でも欧米諸国のように再生可能エネルギーが大量導入されるようになると仮定し、その上で負荷変動が生じた際の周波数変動について研究しています。また、余剰電力発生時の停電リスクに対するインバランス料金の算定も行っていく予定です。
再生可能エネルギーとは何を想定されていますか。
秋山:風力発電です。
風力発電による余剰電力が発生した場合、それを調整するための研究も今後行うということですか。
秋山:ええ。電力が余剰になっても電力の安定供給に影響を及ぼしますので、余剰電力の調整のためにどれぐらい料金がかかるかを研究しています。例えば、大停電が発生すると社会的に大きな損失になりますから、停電が発生しなければどれぐらいの利潤が発生しているかを試算して余剰電力調整の対価を求めようというわけです。
太陽光発電の系統への導入研究に取り組む
斎藤さんはどのような研究をされていますか。
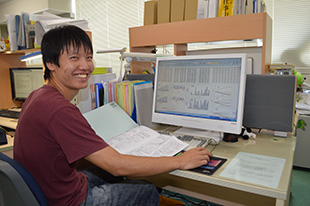
斎藤:配電系統内における三相不平衡改善手法の検討というテーマで研究を行っています。近年、太陽光発電の導入が進んでいますが、今後は太陽光発電からの逆潮流(※1)に起因して三相不平衡問題(※2)が助長することが懸念されています。そうした問題に備えて電力会社と共同研究を行っています。
具体的にはどのような対策を検討されているのでしょうか。
斎藤:太陽光発電に接続するパワーコンディショナー(直流の電気を交流に変換する装置)の有効・無効電力制御(※3)を利用し、系統内における三相不平衡を低減しようと考えています。本来、そうした制御は設置者にとっては売電料金に反映されない無効電力を増加させることになるので、どのようなインセンティブを設けるかなども検討する必要がありますね。
研究されていて、印象的なエピソードはありますか。
斎藤:潮流計算はプログラムを組んで行うのですが、コードのミスや計算の手順のミスなどから最初はエラーが頻発して途方に暮れたこともありました。そこでエラーの原因を一つずつつぶしていき、やっと望み通りにプログラムが動いたときは、大きな達成感が得られました。現在も研究の進捗に合わせてプログラムを少しずつ書き換えて使っています。
(※1)逆潮流とは
分散電源が普及して、余剰電力が配電網に大量供給されるようになると、今まで電気を消費していた需要側が電気を供給することになり、潮流が逆向きになって、電圧上昇などが起きて電力の品質が低下すると言われている。これが逆潮流問題である。逆潮流に関する研究は、大阪府立大学・石亀研究室も行っています。
(※2)三相不平衡については、芝浦工業大学・藤田研究室のインタビューもご覧ください。分かりやすく解説されています。
(※3)有効・無効電力とは
交流の電気には、有効電力(仕事に変わる電力)と無効電力(仕事に変わらない電力)がある。詳しくは東北大学先端電力工学(東北電力)寄附講座のインタビューをご覧下さい。
太陽光発電導入時に起きる問題を制御する
では、塩原さんの研究内容を教えていただけますか。
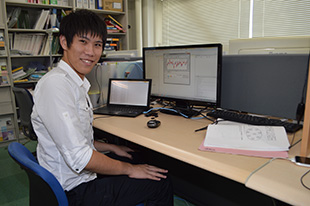
塩原:太陽光発電などの再生可能エネルギーが導入された場合の周波数問題や配電系統の電圧問題の改善などに取り組んでいます。今、斎藤君が説明したのと同じような問題ですね。つまり逆潮流によって生じる周波数のズレを制御しようというわけです。
どうやって制御するのですか。
塩原:将来、太陽光発電が大量に普及した場合の対策として、ガスエンジンを使って制御する方法を検討しています。特に地方の場合、ガスといえばプロパンですから、それも想定しています。
塩原さんは研究で印象的だったのはどんなことですか。
塩原:やはり斎藤君のプログラム同様、私も苦労してやっと開発したプログラムが動いたときは、嬉しかったですね。特に住宅などをモデルにした系統モデルの電圧や位相などを解析する「潮流計算」というものがあるんですが、通常の手法とは別の特殊な計算をする必要がありまして。確認には手で計算することもあったりして、結果が出たときの喜びは印象に残っていますね。企業との共同研究ですから成果の報告にも期限が決められており、そのプレッシャーもありました。
大人数で和やかに研究生活を送っています
みなさんの研究室の特徴について教えていただけますか。塩原さん、いかがでしょう。
塩原:生活感のある研究室です(笑)。
生活感?
塩原:いや、家にいるよりも研究室で過ごす時間の方が長いですから、ここで生活している感じです。それに調理器や冷蔵庫もあるし、なんとベッドまである(笑)。高専の研究室はパソコンだけ置いてあったので、本当にここは生活感がありますね。
なるほど。斎藤さんはいかがでしょう。
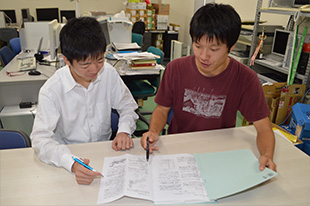
斎藤:大山研究室と辻研究室という二つの研究室が合同で研究生活を送っているので、非常に大所帯です。全部で30人近くいますから。
大人数で和気あいあいという感じですか。
斎藤:そうですね。昼食時には声を掛け合ってほとんど全員がそろって学食へ行きますよ。それで長机を二つ占領したりして。特に上下関係が厳しいということもなく、和やかに研究生活を送っています。このあたりが特徴的ですね。
秋山さんはいかがですか。
秋山:各地のインフラ関連企業と共同研究を積極的に行っているのが特徴です。その中でいろんな企業の方々と関わりを持てるのがいいと思います。特に僕の場合、東日本大震災直後には電力会社の方に直接、状況を聞くことができたのが印象に残っています。
大切なのは研究と自由時間の自己管理
研究室内でのコミュニケーションについてはどんな感じですか。

秋山:普段は週に一回行われている輪講で、研究の進捗状況を教授に発表します。もちろん仲間からの意見ももらいます。飲み会は頻繁ではないですが、交流を深める機会として企画されていますね。
大山研究室ではアウトドアの活動も活発だとか。
塩原:はい、例えば研究室の合宿にスキー合宿があります。卒論が終わったら、年度終わりの遊びということで、企画しています。大山先生はスキーがすごくうまいんです。みんな、ついていくのがやっとで、一人だけスーッと先に滑って行っちゃう(笑)。
斎藤:大山先生はテニスも上手ですよ(笑)。
みなさん研究で忙しそうですが、サークルやアルバイトについてはいかがですか。
斎藤:サークルは学部の卒業で引退しました。アルバイトは週に二回、飲食関係と塾をやっています。もちろん学会などで忙しい時期は研究の進捗に合わせて日程を調整していますので、うまく両立できていると思います。
秋山:私も両立できる研究室だと思います。現在は大学の生協のアルバイトをしているのですが、自由時間と研究活動が両立できています。
専門性を活かして社会の第一線で活躍したい
電気工学を学んでよかったと思うことを教えてください。秋山さん、いかがでしょう。

秋山:就職を考えるときに、自分がどんな仕事に就きたいか、イメージしやすいと思います。やはり電気回路を扱う電気製図などの仕事は、具体的な実務のイメージが浮かびやすいです。もちろん就職活動ですので完全に自分のイメージ通りに行くとは限らないのですが、自分がどんな仕事をしたいか、職業を選択していく上で明確な指針が持てました。
塩原さんはいかがですか。
塩原:やっぱり就職に強いということでしたね。私はインフラ系に興味があったので電力会社の説明会に行ったわけですが、並んでいる学生の中には、基本的な電気の知識を持っていない方もいらっしゃいました。その中で自分の研究をアピールしながら、例えば再生可能エネルギーについて自分の考えを言うと、企業の方が「よくわかってるね」という目で見てくれました。これは大きな強みでしたね。
就職先は電力会社ですね。
塩原:ええ。将来は中央給電指令所に勤務し、電力の安定供給に貢献したいと思います。
斎藤さん、お願いします。
斎藤:私は二人と違って就職とは関係ないことですが、電気・磁気・光などの電気工学分野を学んだことによって、身近で起きている物理現象やどのようにそれらの理論が生活に活かされているのかを学ぶことができた点がよかったと感じています。
斎藤さんは鉄道関係に進まれるそうですね。
斎藤:はい。電気技術者として電気設備の保全や新たな省エネルギー技術に取り組みたいと思っています。今の研究テーマである不平衡の問題は、鉄道の世界にも通じるのです。むしろ電力より鉄道の方が不平衡の問題が大きいかもしれません。就職活動でいろんな鉄道会社の方とお話をする中で、自分の研究を活かせるのではないかと確信しました。大震災の時に電車がずっと止まってしまいましたが、電力会社からの供給が止まっても鉄道だけで発電する設備というのもあります。そういう設備があって電車が動いてよかったなあと、そんなふうに世の中に役立つ仕事がしたいですね。
秋山さんは、どういうお仕事をされるのですか。
秋山:私はプラントエンジニアの道に進みます。電気工学の研究経験を活かし、世界のエネルギー開発に貢献したいと思います。
これからみなさんのお仕事を通じた社会貢献に期待しています。今日はどうもありがとうございました。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。
バックナンバー
- vol.56 近未来の研究で世の中に新しい価値を提供したい。
- vol.55 地球にやさしい先進的な研究で電気工学の可能性を広げたい。
- vol.54 多様な研究を通じて、電気工学の可能性に挑戦したい。
- vol.53 電気工学の研究を通じて、本格的な再エネ時代に貢献したい。
- vol.52 モータの研究を通じて、電気の新しい可能性を拓きたい。
- vol.51 身近なテーマの研究に打ち込み、より快適な社会づくりに貢献したい。
- vol.50 逆風の中でも志を高く持ち、研究活動に打ち込みたい。
- vol.49 技術力で地球にやさしい社会づくりに貢献できるエンジニアを目指したい。
- vol.48 太陽光発電出力予測シミュレーションなどを通じて、再生可能エネルギーの普及に貢献したい。
- vol.47 自由な研究環境の中、自分ならではの研究テーマを通じて成長したい。
- vol.46 高温超電導の研究を通じて、さまざまな社会課題を解決したい。
- vol.45 幅広い電気エネルギーの研究を活かして、 未来の可能性を大きくしたい。
- vol.44 自由な環境で研究に打ち込み、社会からの期待に応えたい。
- vol.43 "雷"の研究を通じて、快適で安心な生活を支えたい。
- vol.42 先進のモーター研究を通じて、 将来の夢を叶えたい。
- vol.41 高専で専門性を磨いて、将来の選択肢をひろげたい。
- vol.40 グローバルな視点を持ちながら、 日本の電力を発展させたい。
- vol.39 風通しのよい自由な研究室で、電気の幅広い魅力を追求したい。
- vol.38 先駆的な研究テーマで、 太陽電池をもっと進化させたい。
- vol.37 生活に身近な研究を通じて、社会のために貢献したい。
- vol.36 パワエレの専門性を武器に社会のニーズにこたえたい。
- vol.35 電磁界を応用した先進研究で 暮らしを便利にするものづくりに貢献したい。
- vol.34 パワーデバイスの先進研究で、省エネ社会を目指したい。
- vol.33 高電圧・大電流を学んで 社会に大きな貢献をしたい。
- vol.32 電気の研究を通じて交流を広げ、 日本の未来に役立ちたい。
- vol.31 風力発電の未来を、もっと広げたい。
- vol.30 電力技術で世界の エネルギー問題を解決したい。
- vol.29 超電導技術で、 未来の社会を支えたい
- vol.28 先進の技術と知識で、 これからの電力を支えたい。
- vol.27 パワエレ技術を活用して、 社会に貢献したい。
- vol.26 放電プラズマで、 夢の技術を実現させたい。
- vol.25 電力システムの研究を活かし 社会の第一線で活躍したい。
- vol.24 自分たちが開発した技術を、世の中へ出したい。
- vol.23 電力を学んで安定供給を支えたい。
- vol.22 世界中の人の生活を支える技術者になりたい。
- vol.21 電気工学で社会インフラを支えたい。
- vol.20 世界に通用するエンジニアになりたい。
- vol.19 電気工学で様々な社会問題を解決したい。
- vol.18 太陽光発電・風力発電を、普及させたい。
- vol.17 日本に新たな電力システムをつくりたい。
- vol.16 電気を上手に使う、省エネ社会を実現したい。
- vol.15 電気で土壌汚染を解決したい。 CVケーブルを守りたい。
- vol.14 電気工学で世界を舞台に活躍したい。
- vol.13 日本、そして世界の電力・エネルギー分野に貢献したい。
- vol.12 送電設備の建設にかかわりたい。電気の面白さを子供たちに伝えたい。
- vol.11 発展途上国を助けたい、 地元に貢献したい、日本の電力を支えたい。
- vol.10 生活を豊かにする製品をつくりたい。 社会インフラを支えたい。
- vol.9 電気工学で環境問題を解決したい!
- vol.8 将来の夢へ、電気工学の知識を活かしたい
- vol.7 これからの日本の電気を私たちが支えたい!
- vol.6 世界中のインフラを、システム工学で支えたい。
- vol.5 超伝導で、がん治療に貢献したい。省エネルギーを実現したい。
- vol.4 電気で、身近な暮らしを楽しくしたい。女性技術者として活躍したい。
- vol.3 最先端プラズマ技術で、社会に貢献をしたい!
- vol.2 夢は、海外で暮らしたい。世の中に新しい 仕組みを創りたい。電気工学が役に立つ!
- vol.1 電気工学は、社会に役立つ研究であり、手に職がつく学問だと実感しています。
バックナンバーを表示する条件を絞り込む
研究キーワードで絞り込んで表示
電力系統(32)電力機器(41)パワーエレクトロニクス(8)超電導(5)
燃料電池(1)風力発電(10)太陽光発電(20)電気自動車(4)
蓄電池(バッテリー)(4)電気利用(機器)(4)IT(3)医療機器応用(4)










