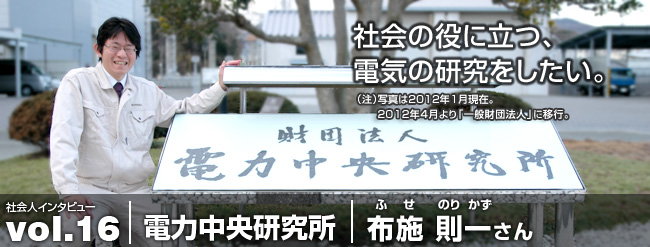vol.16 一般財団法人 電力中央研究所
2012年5月31日掲載
一般財団法人 電力中央研究所(以下:電中研)は、電気をはじめとするエネルギーや環境に関わる研究開発を行う研究機関です。早稲田大学・大木研究室出身の布施則一さんは、博士課程を経て2010年4月に電中研へ入所しました。現在、テラヘルツ電磁波の研究に取り組んだことで得られた知見を武器に、様々な計測現場で活躍中です。東日本大震災からの復旧にも貢献しています。
プロフィール
※2012年1月現在。文章中の敬称は略させていただきました。
“電気はすべての源流”と感じて電気工学の世界へ

最初に、布施さんが電気工学分野を志望された理由を教えてください。
布施:もともと物理が好きでした。その中で電気は、可能性の大きさというものを感じました。つまり全ての源流に電気があり、その先に光など他分野が広がっているようなイメージですね。それで電気を学ぼうと思い、早稲田大学の電気・情報生命工学科へ入りました。
早稲田の大木研究室では、どのような研究をされていましたか。
布施:「ナノコンポジットによる次世代絶縁材料」の研究です。ナノコンポジットというのは、いわゆる強化プラスチックで、身近なところでは車のバンパーや飛行機の機体などに使われ始めています。従来の強化プラスチックはガラス繊維のようなものが入っていて非常に軽くて丈夫なのですが、私は次世代のものとして、もっと小さいナノ単位の粒子を入れた絶縁体についての評価を行っていました。
ナノ単位の粒子を入れることで、絶縁体にはどのような効果があるのですか。
布施:耐部分放電性(コロナ放電による劣化に耐える絶縁材料の能力)が増すことですね。また、電力機器には様々な絶縁体が使われているので、色々な応用が考えられます。最終的には機器全体の能力を上げることが期待されます。
研究室での印象深い思い出はどのようなことでしたか。
布施:一番楽しかったのは光物性評価研究をしている時でした。愛知県岡崎市にある分子科学研究所(UVSOR)に数週間泊まり込んで、高真空の精密機器を動かしながら、漏れ電流にも関係する材料欠陥がどういうメカニズムで出てくるのか解明しようと取り組みました。私が光物性の観点からアプローチしていたのに対し、他の研究機関の研究者は電気の観点からアプローチされていて、結果的にそれらを比較評論する論文も書けました。研究テーマはこれと異なりますが、現在取り組んでいるテラヘルツ電磁波研究で分子シミュレーションができたのも印象に残っています。

かなり充実した研究生活だったようですね。
布施:環境には恵まれていて、研究に没頭できました。指導教官からは常に高い次元を考えながら研究するように言われており、いくつかの計測装置を自由に使いながら取り組みました。必ずしも計測がメインだったわけではないのですが、先ほどの分子シミュレーションのように、実験結果を予測する研究も出来たのはよかったですね。
「電気学会優秀論文発表賞」も受賞されましたね。
布施:はい、一つだけですが賞をいただくことができました。当時は電気学会の委員の割り当てで3ヵ月に一回論文発表のノルマがあり、そのたびに新しいネタを出さなくてはならなくて大変でした。印象深い思い出として今も残っています。
ポスドク問題を乗り越えて、電中研で人の役に立つ研究へ

博士課程修了後、1年間大学に残って助手をされていますね。
布施:電気の研究をしていたのが、いつの間にか分子シミュレーションの分野をやるようになっていて、面白かったのでもうちょっと研究を続けたいと思ったからです。
なぜ、電中研へ入られましたか。
布施:基本的には、人の役に立つ研究がしたかったのです。大学で教育的な仕事に関わりながら研究することも大切ですが、私はより研究に特化した仕事をしたいと思って、電中研へ入りました。
電中研のことは以前からご存じでしたか。
布施:修士1年の頃から電中研とは関わっていました。電中研を定年退職されて大学に来られていた先生もいましたし、私も直接メールで電中研の人とやりとりすることもありましたので。
ポスドク問題(※)が叫ばれていますが、就職への不安はなかったのですか。
布施:すごくありました(苦笑)。だから電中研の面接は一球入魂でした。仮にここを落ちていたらどうなっていたか、想像もつきません。
大学に残るという選択肢もあったと思いますが。
布施:就職を選んだ理由は、研究を究めたかったからです。プロフェッショナルな方たちが周りにいる環境はどうだろうかと考えました。現状の就職状況ですと勇気のいる行動ではありましたが、テラヘルツ電磁波の研究が、私の強みになってくれました。
※ポスドク問題/大学の博士号取得者の就職が年々深刻化している問題。大学院進学者が増加する一方、博士号取得後の大学での雇用が増えず、企業等への就職先も少ない状況であること。
研究成果を活かして東日本大震災からの復旧に貢献

現在は電中研でどのような仕事をなさっているのでしょう。
布施:遠赤外線の光である「テラヘルツ電磁波を用いた塗膜発錆(とまくはっせい)の非破壊検出」をメインに担当しています。テラヘルツ電磁波は、プラスチックは透過しますが鉄錆には吸収されるという特性を持っています。ですから、塗膜をはがさずに内部の錆(さび)の計測ができます。それで各種電力機器の補修作業の効率化や妥当性の向上に役立てようというのが目的です。
テラヘルツ電磁波を使うことによって、見えない部分もどれくらい錆びているかがわかるというわけですか。
布施:そういうことです。例えば送電の鉄塔は、錆びたところを削って何度も塗装していますが、塗膜の下が錆びてしまっていると表面を見ただけではわかりません。そこでテラヘルツ電磁波を利用することで塗膜の下を透かして見る──つまり“非破壊検出”するわけです。もちろん対象は鉄塔だけでなく、変圧器などの電力機器全般です。例えば油が入っている変圧器だと錆びて穴が空くと電気事故になりますから、常にメンテナンスで再塗装しなくてはなりません。その補修作業を合理化・最適化することでコスト削減につなげようという狙いがあります。
なるほど。非常に実用的ですね。
布施:話は変わりますが、最近では東日本大震災の際に津波で被災した発電所の復旧をお手伝いする目的で、ケーブルや機器の浸水確認や洗浄効果確認なども行いました。人間の腰や頭の位置まで津波が押し寄せてきたわけですから、発電所の電力機器も絶対に海水をかぶっているはずです。しかし乾いてしまったら、どの程度波をかぶったか、塩分が残って付着していないか、目で見ただけではわかりません。そこで洗浄で出てくる茶色い物質が海水含有物なのか機器の錆なのかを、材料の観点から判定しました。


テラヘルツ電磁波を用いた計測のシーン
震災からの復旧に貢献されたというのは、とても意義深いことでしたね。実際の現場ではやはり一刻を争うような、緊迫したやりとりがあったのではないですか。
布施:そうですね。早期復旧という大命題がありましたので、非常に緊張感あふれる仕事でした。震災直後に電力会社さんから「機器が浸水してしまったので確認して欲しい」というような依頼があり、電中研の担当者がすぐに飛んでいって、取り組みが始まりました。計測の結果が出たのが7月頃で、そのほぼ最終の報告には私も同行したのですが、先方は会議室に入り切れないぐらいの方が報告をお待ちになっていて、びっくりした記憶があります。やはり非常に重要な仕事のお手伝いが出来たのだと、改めて実感しました。
ご自分の研究が震災からの復旧に貢献できたと。
布施:はい。今年の1月に新聞報道で、発電所が再稼働したという話を目にしました。我々としては一段落です。研究の成果をこういう形で反映させることができて、非常によかったと感じています。
今までの仕事の中で印象に残っているエピソードは、どのようなことでしょう。
布施:一番印象深いのは、先輩方と現場測定に行ったことですね。四国の高知や九州の鹿児島などの遠方へ行き、発電機や大型変圧器の健全性の試験などに立ち会わせてもらいました。大学の研究室では先端計測で先進材料を扱っていましたが、現場ではとにかくシンプルでスピーディーな発想が求められます。例えば漏れ電流計測一つとっても、やり方には単純なものから高額な機器を使って材料の内部まで見ようというものまでテクニックはいろいろあるわけです。その中で、現場においては、結局はシンプルなものが一番いいわけです。こういった現場対応のシンプルな計測から、最先端の研究の両方に取り組めるのが、今の仕事の魅力ですね。
一日の仕事の流れはどんな感じですか。
布施:朝は8時前後に出勤します。仕事のスケジュールは個人の裁量に任されている部分が大きいので、今日は実験をすると決めたら一日中実験に取り組み、報告書を書くと決めたらずっと書いています。常時取り組んでいるテーマは2から3ですね。今は、先ほどお話しした津波関連の仕事が一段落したところです。
入り口は電気でも、その先に様々な道が広がっている

大学での電気工学研究が現在のお仕事に活きていると感じますか。
布施:直接的ではないかもしれませんが、大学で電気計測をずっとやっていたことは今につながっていると思います。つまり先ほどの高真空の装置の件でも、そこで起きている現象は全部電気信号に現れるわけです。そういう意味で大学での電気の知識が自分ならではの視点の基礎になっていると思います。
これから電気工学を学ぶ方にメッセージをお願いします。
布施:ちょうど私が大学に入った頃、学科の名前が「電気工学科」から「電気・情報生命工学科」に変わりました。そんな背景もあって感じるのですが、入り口が電気であってもその先にはいろいろな広がりがあると思うのです。そこには技術だけでなく、人間的なつながりも広がっています。電気工学を自分の本拠としながら、いろいろな道に進めると思います。
電気工学は守備範囲も、可能性も、非常に広いということですね。
布施:はい。将来の選択肢も多岐にわたっていると言えるでしょうね。先ほど先輩方と現場測定に行くという話をしましたが、これは若手のOJT(※)の一環でもあります。つまり様々な現場へ行くことで、私の持っているテラヘルツ電磁波研究の知見を活かせる場がつくれるかもしれないという発想で行われています。私自身、新たなニーズを現場で見つけて、もっと多くの人に役立ちたいと考えています。
※On the Job Training = OJT (※実務経験を積む事で、業務上必要とされる知識や技術を身につけるトレーニング)
今日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。とても臨場感のあるお話でした。これからの布施さんのご活躍を期待しています。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。
バックナンバー
- vol.55 雷の謎を解明して、電力インフラを守りたい。
- vol.54 放送事故は絶対に起こさない。強い覚悟でテレビ局を支えたい。
- vol.53 日々の確実な作業の積み重ねで、地下鉄というインフラを支えたい。
- vol.52 電気工学を活かして技術の発展に女性の視点を反映したい
- vol.51 東西日本間の電力融通を通じて安定した電力供給に貢献したい。
- vol.50 情報科学の知見を活かして電力業界のDX化に貢献したい。
- vol.49 電力業界の新たなルールへの対応の検討を通じ、カーボンニュートラルの実現に貢献したい。
- vol.48 変電技術者として変電所の運営に携わり、電気のある明るい生活を支えていきたい。
- vol.47 空港という重要施設を電気のスペシャリストとして守っていきたい
- vol.46 海底ケーブルのスペシャリストとして電力インフラを支えていきたい。
- vol.45 「ワクワクしつつ冷静に」をモットーに電力の安定供給に貢献したい。
- vol.44 “縁の下の力持ち”として測定器づくりによって社会を支えていきたい。
- vol.43 電力インフラを支える仕事を通じて、環境保護などの社会貢献を続けていきたい。
- vol.42 誰からも認められる女性技術者となり、 発展途上国の人々の暮らしに貢献したい。
- vol.41 電験1種取得者としての専門性を活かし、 電力業界で必要とされる人材であり続けたい。
- vol.40 電気工学の知識をもっと身につけ、 信頼される技術者になりたい。
- vol.39 大容量の電力貯蔵を実現するNAS電池の普及を通じてエネルギー問題の解決に貢献したい。
- vol.38 電気工学の知識を活かし、設備設計のプロとして活躍したい。
- vol.37 電動化が進むクルマの、これからの進歩を支えたい。
- vol.36 電力を支える使命を持った 信頼される存在になりたい。
- vol.35 世界に広がる活躍のステージ。 社会貢献への期待に応えたい。
- vol.34 四国の電力を支える使命を持って、火力発電の未来を拓きたい。
- vol.33 世界中のヒトに信頼される、建設機械を設計したい。
- vol.32 変電設備の最前線で、 電気の安定供給に尽くしたい。
- vol.31 都市レベルでものごとを考えられる、広い視野を持った電気設備設計者になりたい。
- vol.30 高電圧・高電界分野の技術開発で、 電力機器を進化させたい。
- vol.29 電力系統解析の研究者として、 社会や現場のニーズに応えたい。
- vol.28 電力・エネルギーの専門家として、社会に広く情報発信したい。
- vol.27 世界の海洋開発と海上物流を、最先端の電気技術で支えたい。
- vol.26 電力系統を守って人々の生活を支えたい。
- vol.25 新しい制御技術で、 環境にいいクルマを実現したい。
- vol.24 世界の産業を支える 技術者として活躍したい。
- vol.23 日本が誇る電力技術を、 世界に広めたい。
- vol.22 宇宙を駆ける、世界初のものづくりをしたい。
- vol.21 電気工学を活かして、交通安全を支えたい。
- vol.20 製鉄現場を電気技術者として支えたい。
- vol.19 エネルギー・環境問題の解決と、 日本の産業を強くしたい。
- vol.18 電力の安定供給を支えたい。
- vol.17 ものづくりの現場に、 電気の専門家として貢献したい。
- vol.16 社会の役に立つ、電気の研究をしたい。
- vol.15 電気工学で、地球環境を守りたい。
- vol.14 世界に広がる省エネ機器をつくりたい。
- vol.13 世界中の社会インフラを支えていきたい。
- vol.12 電気工学で、半導体の進化を支えたい。
- vol.11 電気工学で、日本の鉄道を支えたい。
- vol.10 世の中ではじめての電力機器をつくりたい
- vol.9 電気を広めて、紛争のない世界を実現したい。
- vol.8 宇宙空間で動く、究極の電源をつくりたい!
- vol.7 風力発電で、エコの輪を世界へ広めたい。
- vol.6 電気工学で、日本のケータイを世界へ広めたい。
- vol.5 夢の超電導ケーブルを、世界中で実現したい!住友電気工業株式会社 西村崇さん
- vol.4 エコキュートをもっと便利に。電気工学で地球環境を守る。
- vol.3 電気は、社会に不可欠なライフライン。だから、私は高電圧・大電流に向き合う。
- vol.2 電気工学を応用して、世界一のハイブリッドーカーを開発したい!
- vol.1 電気工学は一生の財産。どこへ行っても使える学問です。