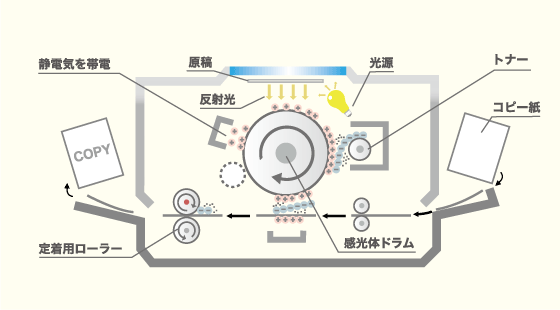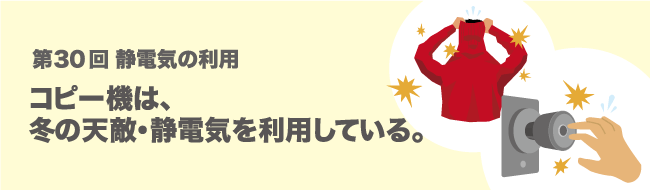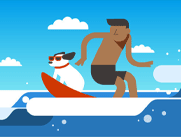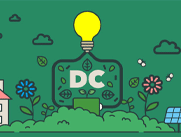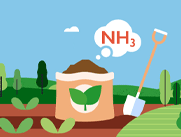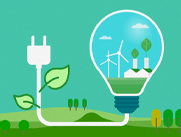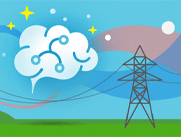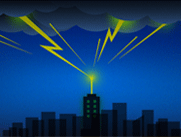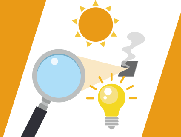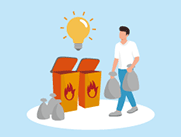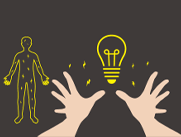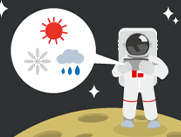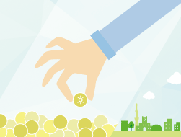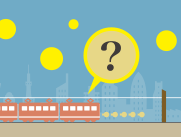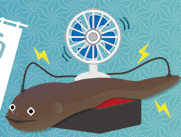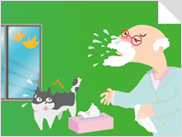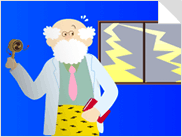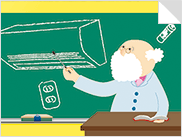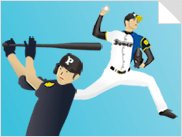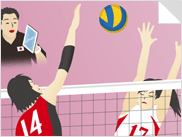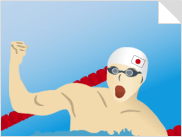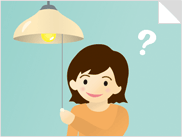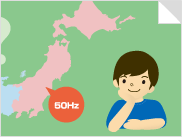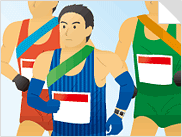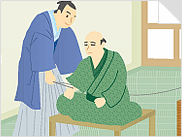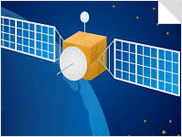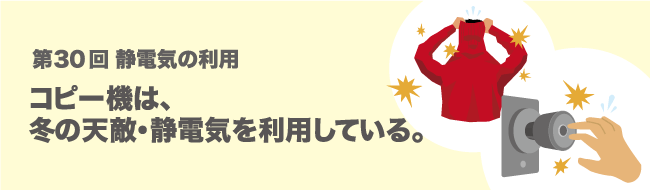
2019年12月掲載
日本全国、本格的な冬に突入し、空気が乾燥してきていますが、セーターの着脱時などに発生する静電気に悩まされる方も多いのではないでしょうか。
実はこんな厄介な静電気も、私たちの生活を便利にしてくれています。
その代表例がコピー機です。
コピー機の仕組みとは?
仕事や勉強に欠かせないコピー機。実は、静電気を利用してつくられています。
コピー機を開けると、大きな筒があります。これを感光体ドラムと言います。
この表面には感光物質がぬってあり、マイナスの静電気を帯電させる役割を持っています。
文書をガラス板の上にのせてコピーをスタートすると、原稿にレーザー光が当てられます。すると、感光体ドラムに原稿の白い部分等から反射されたレーザー光が投影され、静電気が消えます。
一方、その他の光が当たらない部分は、静電気が帯電している状態になります。そこに、プラスの電気をもった黒い粉(トナー)をくっつけると、帯電している部分だけにくっつきます。
これでコピーが完成です。最後は、熱と圧力を加えてトナーを定着させます。
尚、カラーレーザープリンターも基本的な仕組みは同じです。
このようにコピー機で大活躍の静電気ですが、これ以外にも身近なところですと、チリやホコリを吸着する"静電モップ"や、産業用途ですと排出ガスから粉塵、煤塵、ミストなどを捕集する"集塵装置"など、多岐にわたる用途で利用されています。
静電気は確かに厄介な面を持ちますが、一方で有効に利用すれば私たちの生活を便利にする力も持っています。
ちなみに、静電気は夏でも発生しています。しかし、湿度が高い夏は、体に静電気が帯電してもすぐに空気中の水分を通じて逃げてしまうため、パチッとならないのです。
静電気は、古代ギリシャの哲学者・タレスが琥珀を磨いていたときに発見したと言われています。そこから2000年以上、静電気に関する研究・開発は、電気工学を中心に今日も続けられています。
バックナンバー一覧
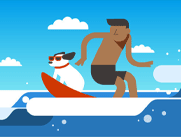
[2025年7月載] 第41回 波力発電のメリット・デメリット
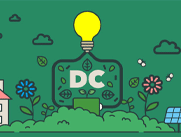
[2024年11月載] 第40回 省エネと直流
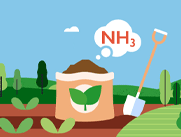
[2024年7月載] 第39回 アンモニアの可能性
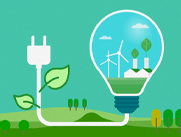
[2023年10月載] 第38回 産業分野(工場)の電化
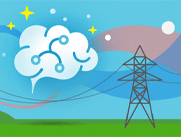
[2023年7月載] 第37回 人工知能と電気工学

[2022年11月載] 第36回 ヒートポンプの応用
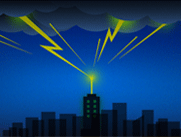
[2022年7月載] 第35回 避雷針の仕組み
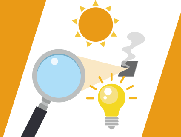
[2021年11月載] 第34回 虫めがね実験と太陽熱発電
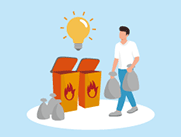
[2021年7月載] 第33回 ごみ発電のメリット・デメリット

[2020年12月載] 第32回 引力と潮力発電
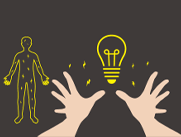
[2020年7月載] 第31回 生体の電気現象と医療機器

[2019年12月載] 第30回 静電気の利用
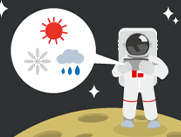
[2019年7月載] 第29回 太陽とプラズマ

[2018年12月載] 第28回 マイクロ波の利用
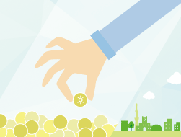
[2018年7月載] 第27回 環境発電(エネルギーハーベスト)とは
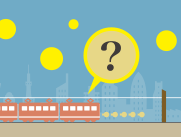
[2017年12月載] 第26回 電車が動く仕組み

[2017年8月載] 第25回 雷の不思議

[2016年12月載] 第24回 地球とプラズマ
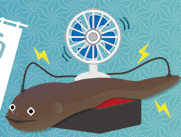
[2016年7月載] 第23回 電気魚の不思議

[2015年12月載] 第22回 モーターと回生ブレーキ

[2015年8月載] 第21回 電気通信の仕組み

[2014年12月載] 第20回 電気の未来社会

[2014年8月載] 第19回 スピーカーとフレミングの法則
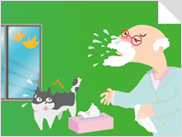
[2014年1月載] 第18回 電気のトリビアその3
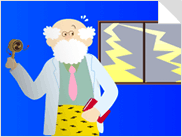
[2013年11月載] 第17回 電気のトリビアその2
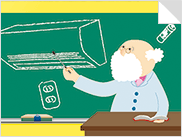
[2013年9月載] 第16回 電気のトリビア
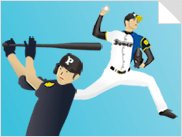
[2013年3月載] 第15回 野球と電気エネルギー
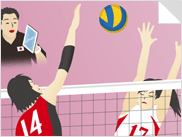
[2012年9月載] 第14回 オリンピックと電気工学その2
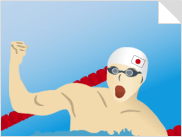
[2012年7月載] 第13回 オリンピックと電気工学その1
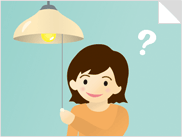
[2012年5月載] 第12回 震災と電気工学その3

[2012年1月載] 第11回 震災と電気工学その2
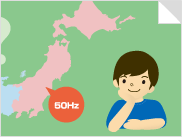
[2011年11月載] 第10回 震災と電気工学その1

[2011年6月載] 第9回 LED照明のメリット/デメリット
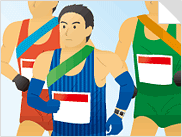
[2010年12月載] 第8回 電力系統と駅伝
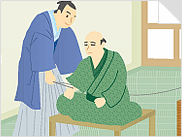
[2010年9月載] 第7回 医療機器応用の歴史
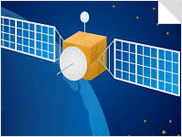
[2010年4月載] 第6回 人工衛星と太陽電池

[2010年4月載] 第5回 宇宙船と燃料電池

[2009年12月載] 第4回 ヒートポンプと打ち水

[2009年5月載] 第3回 電気自動車とミニ四駆

[2008年10月載] 第2回 パワーエレクトロニクスとボランチ

[2008年7月載] 第1回 超電導と浮遊術
すべて表示する
5件だけ表示
サイトの更新情報をお届けします。
「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。
メールマガジン登録