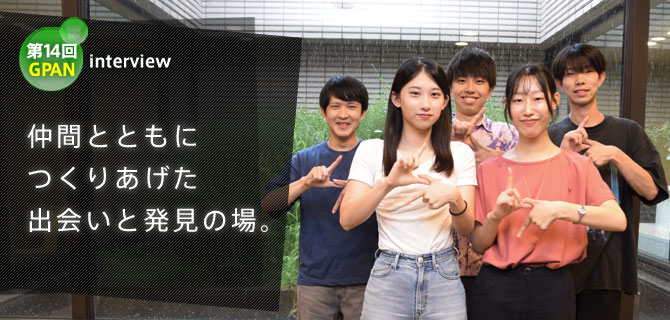学生幹事インタビュー
コミュニケーションの大切さを学ぶ
北海道大学 M1 山田 彩人(やまだ あやと)

私は学生幹事代表としてGPAN全体の運営に関わりました。自分が中心となって方針を決めたこともありましたが、他の学生幹事の皆さんの協力や意見があってこそ実現できたことは間違いありません。仲間とともにつくりあげていくプロセスそのものが、非常に貴重な経験になりました。
最も大変だったのは、学生幹事同士の意思疎通でした。それぞれ研究や就職活動など多忙な日々を送っており、直接顔を合わせて打ち合わせをする機会がほとんど持てない中、オンラインで議論を重ね、意見をすり合わせていくことには苦労しました。この経験を通じ、相手の立場や状況を理解しながら効率的にコミュニケーションを取る重要性を学びました。離れたメンバー同士であっても、目的を共有し協力すれば大きな成果を生み出せることを実感できた点は、大きな収穫だったと思います。
ディベートテーマについても、学生幹事で幅広く意見を出し合いながら、賛否が分かれやすく議論の深まるテーマかどうかを丁寧に検討していきました。より広い視点を大切にAIに関するテーマも導入するなど、研究者として多角的に考えるきっかけになったのではないかと思っています。
今は純粋に楽しかったという気持ちが一番です。特に学生参加者の皆さんが限られた時間の中で仲間と協力し、完成度の高い成果をつくりあげてくれた姿には深く感動しました。今回のGPANが、全国から集まった仲間や産業界・教員幹事・パワーアカデミーの方々とのつながりを広げる機会となったのであれば幸いです。
学生幹事の仕事は大変なこともありますが、それ以上にやりがいがあり、自由度も高いので非常に楽しめる経験になると思います。来年も多くの方に存分に楽しみながら取り組んでいただければと思います。
学生幹事ならではの醍醐味を実感
早稲田大学 M1 岡本 光一郎(おかもと こういちろう)

昨年GPANに参加してディベートをとても楽しめたので、次は自分がテーマ決めや運営に携わりたいと考えたことが、学生幹事となった一番の理由でした。先輩幹事がイキイキと楽しそうに働く姿を見たことも、動機の一つです。
就活に向けてのインターンシップ期間中でもあり、非常に忙しい毎日を送っていたので、資料作成や幹事同士の打ち合わせを行うことは大変でした。しかし、お互いに助け合い、切磋琢磨しながら取り組んだことで、乗り切ることができました。
特に印象に残っているのは、やはりディベートです。学生幹事がいくつかテーマを持ち寄り、打ち合わせを重ねながら絞っていきました。水素タウンの見学が決まっていたので、水素に関するものを1つ、それ以外のテーマを2つ決めました。
私はディベートの本番でタイムキーパーを務めました。AIという今までにないディベートテーマを導入し、実際にディベートがうまくいくか心配でしたが、大いに盛り上がって安心しました。タイムスケジュールに変更があったものの、幹事同士で臨機応変に対応できてよかったと思います。忙しい中で準備してきたことが形となり、参加者が全力で議論している姿を見られたことは、学生幹事としての大きな喜びでした。
学生幹事の仕事は簡単ではなく、準備も大変です。しかしその分、本番で得られる喜びが大きいことは間違いありません。仲間と協力しながら1つの大会をつくりあげていく経験は貴重なので、ぜひ大勢の方に楽しみながら取り組んでいただけたらと思います。
裏方としての業務を体験できました
早稲田大学 M1 森田 晃世(もりた あきよ)

昨年参加した際、学生幹事を務めてくださっている先輩方の姿を見て、運営側の仕事も楽しそうでやりがいがあるのではと感じ、今年は自分も学生幹事に挑戦することにしました。
担当した業務は景品の発注や当日の資料の作成等です。準備期間が非常に短い中、慣れない仕事を進めていくことは簡単ではありませんでした。一方で、このようなイベントを行う際の手順やタイムスケジュールを実体験として学ぶことができ、今後に活かせる経験が得られました。また、役員や先生方の裏方さんとしての努力も知ることができました。
ディベートテーマについては、まず参加者が興味ある領域は何なのかについて、事前アンケートを用いて収集しました。その後、全員でテーマを持ちより検討しました。本当に是非が分かれるテーマなのか、検討する余地があるテーマなのか、議論して決めていきました。
こうして様々な準備をしてきたので、学生参加の皆さんが「楽しかった」と笑顔で帰途につけるGPANにできればいいなと思って本番を迎えました。
本番を終えた今は、無事に終了してホッとしたという感想に尽きます。初めから時間が大幅に押してしまうなどのトラブルもありましたが、なんとか終えることができました。
学生幹事は、参加者として見ているだけでは知ることができない裏方の業務を体験できる貴重な機会です。大きなやりがいが得られますので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。
多くの方々と交流できることが一番の魅力です
徳島大学 M2 武本 結衣(たけもと ゆい)

昨年度のGPANに参加し、私も企画運営に携わりつつ他大学の学生と深く交流したいと思い、学生幹事に立候補しました。
私が担当したのは、参加要領等の資料作成および参加学生の窓口担当です。参加要領の作成については、学生幹事内で施設見学先や2日間のスケジュール、注意事項等について話し合い、それを資料化しました。参加学生の窓口担当としては、作成した資料等の参加学生への送付や、事前アンケートの回答依頼等のメールを送る仕事に携わりました。問い合わせがあった際は、他の学生幹事に内容を共有した上で対応するようにしました。
痛感したのは、リモートでの打ち合わせの難しさです。主にLINEを使用してやり取りしていましたが、オンタイムのコミュニケーションではないため、会話にラグが生じてしまう点には苦労しました。
ディベートについては、3回戦分のテーマの方向性を大まかに決めた後に各自でテーマを考えて共有し、Web会議を通して決定しました。Web会議では、各自が考えたテーマについて「意見の偏りが出ないか」という点に重点を置いて話し合いました。特に大きな問題はなく、無事に2日間を終えることができて本当によかったと思っています。多くの方々と交流できたことは、とても楽しかったです。
私が思うGPAN学生幹事の魅力は、多くの方々と深く交流できること、他団体ではめったにできない経験が得られることです。
GPANの企画・運営に携わる期間は1年もないので、次の学生幹事の皆さんにはぜひ全力で取り組んでいただきたいと思います。大変なこともあるでしょうが学生幹事同士で協力し合い、納得のいく第15回GPANとしていただけるよう、願っています。後悔のないように、楽しんでください。
大変だからこそ楽しみも大きい
広島大学 M1 木村 仁紀(きむら まさき)

昨年学生幹事を務めた先輩が「苦労するけれど成長できる」と教えてくださったことがきっかけで、私もGPANの学生幹事に挑戦することにしました。担当したのはディベート会場などの下見、ディベート採点関係の資料作成、ディベートの司会です。
ディベートテーマは、オンラインでの話し合いを重ねて決定しました。みんな就活などで忙しかったですが、インターンシップ後に時間を捻出するなど、工夫して話し合いました。これまでのディベートテーマは電力に深く関連したテーマであったのに対し、今回は工学などの大きな枠組みで問題をとらえることを意識しました。
私はこれほど大きなイベントの幹事をしたことがなかったため、事前の準備がこんなにも大変なのだと驚きました。メンバーが忙しくて話し合いの時間が限られていたことには、苦労しました。しかし、大変だからこそやるべきことを整理し、情報を明確にまとめて、迅速に意思決定を行うよう心がけました。
2日目のディベートでは司会を務め、時間通り進行できるか不安でしたが、無事ディベートを終わらせることができてホッとしました。共に準備を重ねた学生幹事の仲間や支援してくださった教員幹事・事務局の皆様のおかげだと感謝しています。
次回の学生幹事を担う皆さんにとって、研究や就職活動と両立させながら準備を進めることは簡単ではないと思います。けれども仲間との絆が深まり、大きな成長につながることは間違いありません。他大学の学生と交流できる機会は大変貴重ですので、大変さも楽しみながら取り組んでいただけたらと思います。