電気の施設訪問レポート vol.6

関西電力堺港発電所と堺太陽光発電所を訪問しました
2011年10月、パワーアカデミー事務局は、大阪府堺市にある関西電力 堺港発電所と堺太陽光発電所を訪問しました。堺市の臨海部に位置する堺港発電所は、低炭素社会の実現とより低廉な電力の供給に向け、天然ガスを燃料とした熱効率の優れたコンバインドサイクル発電方式を採用した火力発電所です。
また、2011年9月には、同じ臨海部で国内最大級のメガソーラーである堺太陽光発電所が運転を開始しました。本レポートでは、完成したばかりの堺太陽光発電所と、コンバインドサイクル発電方式を採用した火力発電所の仕組みや特徴などを紹介します。その他、見学させて頂いた堺港発電所の中央制御室やPR館『エルクールさかいこう』もあわせて紹介します。
堺太陽光発電所

堺太陽光発電所は、関西電力と堺市との共同プロジェクトで建設されたものです。太陽光発電所としては、日本最大級(1万kW)の規模となっています。この大規模な太陽光発電所は、電気のさらなる低炭素化と太陽光発電を大量に受入れた際の電力系統への影響の検証を目的としてつくられました。堺太陽光発電所がつくられた背景から、主な特徴をご説明します。
そもそも太陽光発電とは
太陽光発電とは、その名の通り太陽電池を利用して、太陽の光を使って発電します。そして発電時にCO2を出さない、エコな発電方法です。今最も注目される再生可能エネルギーの一つです。一般家庭でもソーラーパネルを屋根などに設置すれば電気をつくることができます。さらに、つくった電気は電力会社に売ることもできます。
太陽電池の仕組みを知りたい方はこちら
家庭用太陽光発電を知りたい方はこちら
太陽光発電の課題
しかし、太陽光発電を大量に普及させるためには、解決すべき大きな課題があります。太陽光発電は、太陽光によって発電するため、気象条件によって大きく発電出力(電気の大きさ)が左右されます。そのため、太陽光発電が大量にあると、電圧や周波数の乱れなど、電気の品質が保てなくなる恐れがあります。また、発電コストが高いことや広い用地の確保などの課題も挙げられます。
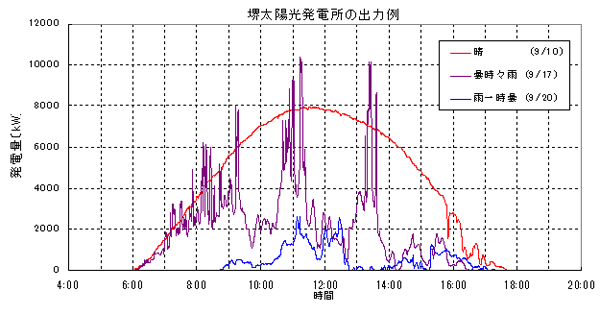
太陽光発電の出力変動について、実際に研究を行っている学生が語っています
課題解決への取り組み

各電力会社では、太陽光発電の普及に取り組んでいます。今回取材した関西電力でも、電気の品質を保ちつつ、太陽光発電がさらに普及するように様々な取り組みを進めています。その一環として、発電量の予測研究や蓄電池を用いた電力需給制御システムの研究などを行っています。
発電量の予測研究では、関西電力管内60箇所に日射量計や気温計を設置・計測し、太陽光発電の大量導入時に電力系統に与える影響を検証しています。また堺太陽光発電所においても、実際の運転データを蓄積することにより、他の発電所のデータなどとあわせて、将来の発電コントロールに役立てる検証をしています。
電力系統への太陽光発電の大量導入に向けた、取り組みはこちら
日本最大級のメガソーラー発電所!堺太陽光発電所の概要
それでは、堺太陽光発電所の概要を紹介します。発電所の広さは、約21万㎡。これは阪神甲子園球場が5個入る大きさです。ここに約7万4000枚のソーラーパネルを設置しています。発電出力は1万キロワット。年間発電量は約1100万キロワットアワーで、堺市の約1%、約3000世帯の家庭の年間電気使用量に相当します。また、堺太陽光発電所を運転することによって、CO2の排出削減量は約4000トンとなると見込まれています。
| 所在地 | 大阪府堺市西区築港新町4丁 【堺第7-3区産業廃棄物埋立処分場(大阪府所有)】 |
|---|---|
| 敷地面積 | 約21万m² |
| 定格出力 | 10MW(1.0万kW) |
| 太陽電池枚数 | 約7万4000枚 |
| 発電電力量 | 約1,100万kWh/年 |
| 運転開始 | 平成23年9月7日(一部運転開始 平成22年10月5日) |
太陽電池の特徴
堺太陽光発電所は、ソーラーパネルにシリコン系薄膜型太陽電池モジュールを採用しています。また、ソーラーパネルの傾斜角は15度を採用し、風圧を軽減することにより、基礎のコンクリート量を削減。さらに、コンクリート基礎に直接モジュールを取りつけることで、鋼製架台を省略しコスト削減を図っています。
パワーコンディショナー・変電設備
太陽電池モジュールで発生した直流の電気は、同じ敷地にあるパワーコンディショナーで交流の電気に変換しています。パワーコンディショナーで変換された電気は、発電所構内の変電設備にて段階的に22kVまで昇圧してから、送電線で変電所まで送電しています。
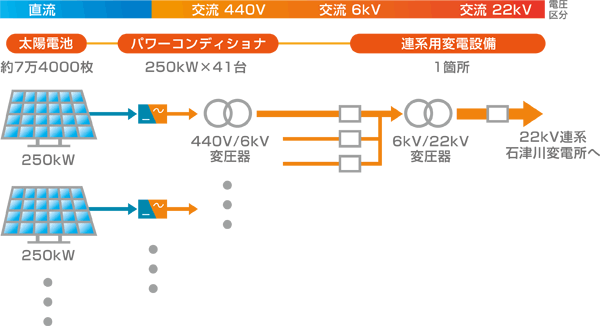
夜間(LED照明)

夜間は、LED照明で文字を表現して、美しい景観となります。LEDの電力は、太陽電池で昼間に蓄電池で貯めておいたものです。
LEDの仕組みを知りたい方はこちら
コンバインドサイクル発電
堺港発電所は、1964年に運転が開始されました。その後、1974年には油焚きから天然ガス焚きへの変更を開始。天然ガスは、発電時のCO2や窒素酸化物の排出が他の化石燃料に比べて少ないため、クリーンな化石燃料といわれています。堺港発電所は2006年からコンバインドサイクル発電方式への設備更新工事を開始し、2010年9月に、5号機まで全てが完成し、総出力200万kWの発電所となりました。
コンバインドサイクル発電方式とは
コンバインドサイクル発電方式とは、蒸気タービンにガスタービンを組み合わせて、熱を有効利用する発電方式です。従来の火力発電は、石油や石炭、天然ガスを燃やして蒸気をつくり、その蒸気の力でタービンをまわします。一方、コンバインドサイクル発電は、まず天然ガスを燃やし、その燃焼ガスの勢いでガスタービンを回し、次にガスタービンを回した後の高温ガスの排熱を利用して蒸気をつくり、蒸気タービンを回して発電します。ダブルのタービンで発電するため、大変、効率の良い発電方式です。そのため、従来よりも少ない燃料で発電が可能となり、CO2排出量を従来の汽力発電方式と比較して約3割もカットできます。
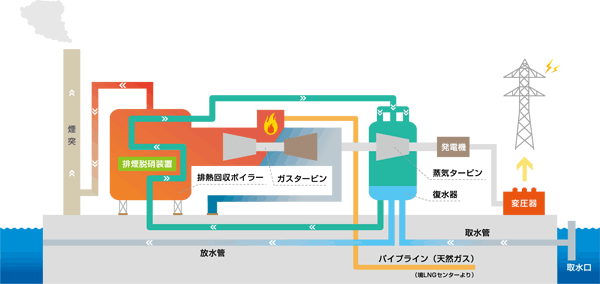
中央制御室
写真は、堺港コンバインドサイクル火力発電所の中央制御室です。中央制御室では、全ての発電設備の運転・監視を24時間365日行っており、中枢といえる箇所です。ほとんどの機器がコンピューター制御されており、必要最小限の運転員で稼働できる最先端の中央制御室です。

堺港コンバインドサイクル火力発電所の中央制御室(手前はオンサイトのシミュレータ施設)

中央制御室横の見学エリアには、タービンの翼の模型が展示されています。
堺港発電所PR館『エルクールさかいこう』
『エルクールさかいこう』では、コンバインドサイクル発電や太陽光発電など、低炭素社会に向けた関西電力の取組みが紹介されています。発電時にCO2を出さない「CO2フリー」のエネルギーを増やしながら、発電時のCO2を減らす「CO2オフ」を進めていく、という取組みです。案内スタッフの説明と映像とで分かりやすく学ぶことができます。

