vol.4 九州大学

学生インタビュー vol.4
電気で、身近な暮らしを楽しくしたい。女性技術者として活躍したい。
九州大学 末廣研究室
舞 香織さん、小手川 誠さん
九州大学の末廣研究室は、静電気工学や高電圧パルスパワー工学のバイオテクノロジーおよびナノテクノロジーへの応用に関する研究に取り組んでいます。これらの最先端テクノロジーは、私たちの身近な生活や暮らしを豊かにしてくれます。
※2009年6月現在。インタビュー中の敬称は略させて頂きました。
きっかけは、ロボットや家電が好き

小手川さんは、大学受験のとき、なぜ電気工学を専攻されたのですか。
小手川 誠(以下、小手川):私は、九州大学工学部の「電気情報工学科」という名前ですね(笑)。元々、私は自分でホームページを作成していました。また、将来はロボットをつくりたいなぁという夢も持っていました。それで、「インターネット=情報」「ロボット=電気」ということで、各々に関わる研究ができると思い「電気情報工学科」という名前に惹かれて進学しました(笑)。
舞さんはいかがですか。
舞 香織(以下、舞):私の実家は、父親と母親と妹の4人家族なのですが、家でPCの修理や配線をつなげるのが私の担当だったというのがきっかけです。父親が仕事へ行くと女3人が残りますよね。それでなぜか私がやるようになって、だんだんと家電が好きになってきたというわけです(笑)。

それから大学院へ進まれるわけですが、末廣研究室を志望された理由は?
小手川:末廣研究室を志望したのは、「カーボンナノチューブ」という最先端の研究をやっていたからです。新しいことをやりたいと思っていました。
舞さんは?
舞:私は学部時代、電力系統のシミュレーションなどをやっていました。ちょうど、このインタビューの大阪大学の方と全く同じ研究です。それで、電力の勉強を活かせる研究室が、九州大学では末廣研究室だったというのが大きな理由です。あとは、実験にも興味がありました。
ナノテクノロジー=10億分の1メートルを操る技術
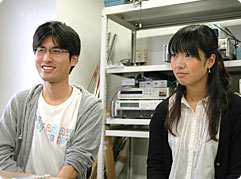
おふたりとも同じ研究をされているのですか。
舞:はい。私たちを含めて3人でチームを組んで、小手川さんがリーダーです。
では、小手川さんに研究内容を伺います。簡単に言うと、どのような研究をなさっているのですか。
小手川:一言で言えば、電気の力を利用してカーボンナノチューブを使ったガスセンサをつくるという研究です。今まで誰もがやっていない、新しい研究です。
カーボンナノチューブとは何ですか。
小手川:カーボンナノチューブとは、カーボン(炭素)でできた、直径がナノメートル(10億分の1メートル、髪の毛でいうと1万分の1のサイズ)のチューブ状の物質です。カーボンナノチューブは、これだけの細さでありながら、ダイヤモンドと同等の強さを持ち、銅の約1000倍の電流を流すことができます。その他にも電気抵抗が少なく、銅の10倍の熱伝導率を持つなど、多くの優れた性質を持っています。そのため、様々な分野に応用が期待されている、新物質です。
凄いですね。例えば今、多くの電気機器には銅が使用されていますが、それがカーボンナノチューブになれば大きな進化が期待されますね。ガスセンサとは何ですか。
小手川:ガスセンサとは、特定の気体の濃度に反応するセンサのことを指します。私たちの身近なところですと、ガス漏れを感知すると警報音で知らせるセンサがありますね。でもそれだけではなく、例えば、汚染物質の検出や麻薬・地雷の探知、個人認証や食品開発など、多くの用途で活用が期待されています。

なるほど。それでは、どのようにカーボンナノチューブを使ってガスセンサをつくっているのですか。
小手川:カーボンナノチューブは小さすぎて、そのままだとセンサに応用ができないのです。そこで私たちは誘電泳動(※)という現象を利用して、カーボンナノチューブをガスセンサに利用しています。誘電泳動で微弱な力を利用することで、ナノサイズの微粒子をコントロールできるのです。
最終的には、どのようなガスセンサが生まれるのですか。
小手川:例えば、アンモニアや二酸化窒素などの環境汚染ガスを、ppmレベル(100万分の1)で高感度に検出できる性能を持つガスセンサの開発に成功しています。ナノレベルに感知ができるガスセンサです。
つまり、皆さんが手掛けている研究は、ナノテクロジーということですね。
小手川:そうです。元々、末廣先生は、誘電泳動を使って、食物から細菌を検出する研究をしていたそうです。今、騒がれている食の安全を守るためです。そこで今度はガスセンサに誘電泳動を応用したというわけです。
※誘電泳動とは、電気力学現象の一種で、不均一な電界中に置かれた浮遊粒子が電界の強い領域もしくは弱い領域に駆動される現象を言う。
留学生との交流、オン・オフを大事にする研究室

ナノメートルオーダーの研究は想像がつかないのですが、実験が多いのですか。
舞:はい、実験がほとんどです。実験は、先ほども言ったように3人のグループでやっています。名前はガスセンサチームです(笑)。
小手川:(笑)。私たちの研究は基本的に出来上がった材料の応用なので、ゼロから新しい材料そのものをつくるのではありません。応用研究ですね。一週間の流れとしては、毎週1回、研究進捗状況を報告するゼミを全員参加で行い、あとはグループで実験を行うという感じです。
アルバイトやサークルなどをする時間は、ありますか。
小手川:大丈夫です(笑)。私は、今アルバイトと実験の日々です。アルバイトは、学部生の情報処理の授業で、TA(ティーチング・アシスタント)を週1回努めています。それから、大学で学んだ知識を生かして電気工学関係の専門学校で実験の指導も行っています。
舞:私は学部時代から続けている、テニスサークルをやっています。九州大学は最近、工学部が伊都キャンパスに集約したので、色々なテニスサークルが集まっています。新しい友達が増えてうれしいです(笑)。

なるほど。では、末廣研究室の特徴を教えて下さい。
小手川:研究室の特徴というと、PCが全てMacということですかね。末廣先生のこだわりです。
舞:だから図形を描くことについては、先生、結構厳しいです(笑)。
Macはデザイナーがよく使うPCですからね(笑)。他に何かありますか。
舞:留学生の方が多いことですね。私が以前いた学部には、外国の方はいなかったのでビックリしました。うちの研究室の半分が、外国人です。それも、多国籍でエジプト、インドネシア、中国の方がいらっしゃいます。
コミュニケーションはどのようにされるのですか。
舞:英語です。私は、そんなに英語がしゃべれないので、とにかくジェスチャーも交えて、気持ちでコミュニケーションをしています。はじめはとまどいましたけど、最近はようやく慣れてきましたね。他の国の方と一緒に生活をする機会はなかなかないので、すごく勉強になります。英語でコミュニケーションをとる大切さを実感しました。
研究室全体で、何かコミュニケーションをとることはありますか。
舞:研究室全員で定期的に旅行や飲み会をやっています。ですから、自然とコミュニケーションがとれますね。この春は、福岡市にある海の中道海浜公園に他の研究室の方たちと合同で行きました、

国営 海の中道海浜公園にて
住宅設備を電気でもっと魅力的なモノに(小手川)
結婚して子供を生んでも、電気に関わりたい(舞)

それでは、電気工学を学んでよかったことを教えて下さい。
舞:電気工学ってすごく幅が広い学問だと思います。PCでシミュレーションをすることもあれば、電気回路をつくることもある。化学的な研究をすることもあります。だから、本当に自分がやりたいことを見つけられる分野ではないでしょうか。
小手川:色々な生活をしている中で、モノの本質が見えることですね。蛍光灯ひとつとっても、どうやって光るのかが分かる。社会で生活をしていく上で、様々なことが見えてきます。
おふたりの将来の夢や目標を教えて下さい。
舞:やはり電気系の会社に就職したいです。女の人が少ない業界ですが、結婚して子供を産んでもずっとやっていける職場で働きたいです。そして自分が携わった製品を世に出したいです。
小手川さんはいかがですか。
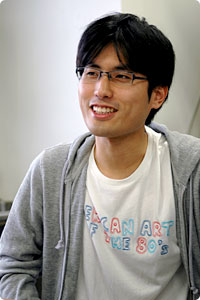
小手川:実は、私は住宅設備関連の会社に就職が決まっています。具体的に言うと、トイレやキッチン、バスなどを扱っている会社です。どうして、その会社を志望したかというと、私は、自分の周りの人達を、電気で喜ばせたいのです。トイレひとつとっても、今は便座を温めたり、ウォシュレットがあったりしますね。これらは全て電気で制御されています。私は、電気を使って、身近なモノをもっと便利で楽しいモノにしたいという夢を持っています。
身近な生活を電気でより良くしたいというわけですね。
小手川:そうですね。人それぞれ使命があると思うのですが、自分の場合は電気を使って世の中に貢献することだと考えています。
ありがとうございました。おふたりの夢をぜひ実現して、電気工学の魅力を社会に伝えてください。

末廣 純也 教授(すえひろ じゅんや)
当研究室では、静電気工学や高電圧パルスパワー工学のバイオテクノロジーおよびナノテクノロジーへの応用に関する研究に取り組んでいます。特に近年は、誘電泳動やマイクロプラズマを利用した生体物質やナノ物質の操作・改質、ならびにBio-MEMSデバイス、ナノデバイス、ナノコンポジット材料などへの応用を目指しています。2009年度は、教職員2名、博士課程2名、修士課程5名、学部生4名で活動しています。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。
バックナンバー
バックナンバーを絞り込む
研究キーワードから探す
大学の所在地から探す
サイト更新情報をお届け
「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。