vol.51 岐阜大学
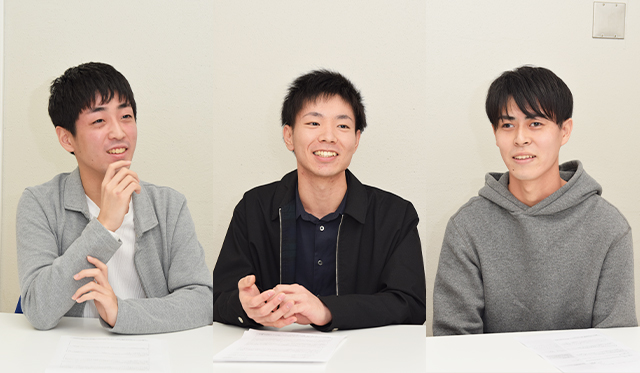
学生インタビュー vol.51
身近なテーマの研究に打ち込み、より快適な社会づくりに貢献したい。
岐阜大学 高野研究室
中江莞さん、吉田尚洋さん、岩瀬徳寿さん
“清流の国”と称される自然豊かな地で、「学び、究め、貢献する」人材の育成に力を入れる岐阜大学。今回はこちらの「高野研究室」におじゃましました。発足してまだ3年というだけあって、研究室内はすっきり広々と快適。いつも明るい雰囲気を作ってくださる高野先生のご指導のもと、皆さん、まっすぐ研究に打ち込んでいらっしゃいます。
※2020年10月現在。文章中の敬称は省略させていただきました。
自由な雰囲気に惹かれて選んだ研究室

中江さんは神奈川県出身。「岐阜は自然豊かで住みやすいですね」。
皆さんが電気工学を学ぼうと思われた理由を教えてください。中江さん、いかがですか。
中江:最初のきっかけは、高校の電気の授業でした。理系分野の中でも特にパズルを解くような面白さがあり、楽しい授業だなと思ったことが、電気に興味を持った理由です。その後大学に進み、ロボコンサークルに所属してプログラミングを学び、『NHK学生ロボコン』などにも挑戦するうち、この知識を電気の分野にも活かせないかと考えるようになりました。
電気とITの両方をやってみたいと思ったわけですね。
中江:はい。電力の分野でもDX(デジタル・トランスフォーメーション)が進んでいくと考え、その分野で研究したいと思うようになりました。
ありがとうございます。では続けて吉田さん、お願いします。

吉田さんは地元・岐阜県出身。電気の使用による環境負荷に興味を抱き、電気工学を志望。
吉田:高校進学の際、工業高校の見学に行ったところ、電気の授業がとても面白いと感じたことがきっかけでした。結局高校は普通科に進学したのですが、理系の科目が得意ということもあって、大学進学では工学部の電気電子・情報工学科に進みました。学部の講義では電気の使用による環境負荷が地球温暖化の一つの要因と知り、この問題をエネルギーの効率的な視点で研究したいと考え、電気工学を志望しました。
ありがとうございます。岩瀬さんはいかがでしよう。

岩瀬さんは愛知県出身。研究の幅広さに惹かれて高野研究室を選びました。
岩瀬:父が生産管理のエンジニアをしており、子供の頃からその話を聞いていたこともあって、大学では迷わずに工学部を選びました。当時は電気自動車や太陽光発電などのニュースをよく目にしていたこともあり、将来は電気のエンジニアの活躍が求められると感じ、電気工学の道を選びました。
高野研究室を選ばれた理由についてはいかがですか。中江さんは研究室の初代メンバーだそうですが。
中江:そうなんです。新しい研究室ができると聞いて、“どんな研究室だろう”と興味津々にお話を聞いたところ、電力と情報の両方について学べると知り、DXについても触れられる機会があるのではと考えました。
吉田:私の場合は、他の電気系の研究室に比べて、ここは電力の研究に特化している点に惹かれました。また新しい研究室なので、先輩を気にせずに自由に過ごせるのではと思ったことも大きな理由です。
岩瀬:その吉田さんの研究発表を見て、研究テーマの幅が広いと感じたことが、私がこの研究室を選ぶきっかけになりました。
社会に役立つことがイメージできる研究
では、皆さんの研究内容について教えてください。
吉田:私はデマンドレスポンス(DR)の理論的な設計方法を研究しています。DRとは、電気料金を変化させたり、報酬を支払ったりすることで、消費電力を需給運営上の望ましい状態に誘導する仕組みのことです。前者を料金型、後者をインセンティブ型としており、これによって電力の需給逼迫問題や再生可能エネルギー余剰問題に対応できるのではと期待されています。実証実験も行われていますが、その際の電気料金や報酬額の決定は電力供給者の知識・経験が頼りにされているのが実情で、私はこれらを理論的に設定する方法を研究しています。

PCのモニターは1人2台が基本。
とてもイメージしやすい研究ですね。面白みはいかがですか。
吉田:やはり社会に直接役立つ研究であるという点が一番のやりがいですね。人に説明しても、共感していただきやすいテーマだと思います。ちなみに個人的にインセンティブ型の仕組みのほうが、効果が高いと感じています。
ありがとうございます。続いて岩瀬さん、研究内容について教えてください。
岩瀬:スマートメータによって記録された、電力需要家の電力消費履歴の解析を行っています。従来の電力メータですと電力消費量履歴の確認は1ヵ月ごとの検針で行われていましたが、スマートメータでは一定の短い間隔で記録され、電力供給者に直接リアルタイムで送られていきます。その解析を行うことで、電力需要管理に役立つ情報を得られるのではないかと思っています。
岩瀬さんの研究も、私たちの実生活に身近な感じですね。
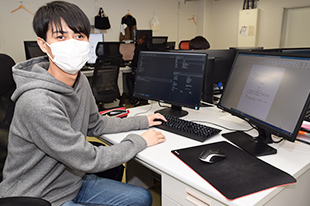
机が広く、長時間の作業も苦にならないとか。
岩瀬:ええ、吉田さんの研究同様、私もその点が面白みです。例えばエアコンの使用状況によって電力消費量は大きく変動するなど、予想したとおりに気候との相関関係が強いことがわかっています。解析に使うデータは電力供給者からいただいているので、社会の需要がそのまま反映されている実感があります。
では、中江さん、お願いします。
中江:はい。私は配電設備に関するビッグデータの活用手法について研究しています。具体的には配電設備の点検記録や保修記録などの情報を用いて、設備寿命を推定する手法や、設備の補修基準を作成する方法などについて検討しています。例えばコンクリート電柱のひび割れから寿命を推定したりするわけです。
皆さん、すぐにでも社会に役立ちそうな研究テーマですね。

中江さんは、3台のモニターを使用。目的に応じて使い分けています。
中江:この状態の電柱ならあと何年は使用できるといったことを推定できるようにするわけですから、社会貢献度の高い研究だと実感しています。
学会発表で、社会からの期待の大きさを実感
研究活動で印象的だったことは何ですか。
中江:共同研究をしている企業の皆さんとのミーティングで、研究で得た知見を発表したところ、「やはりそうだったのか」という納得や驚きの声をいただいたことが印象に残っています。“やった!”と、大きな達成感がありました。
吉田:私は電気学会、エネルギー資源学会で発表する機会を得ました。その際、社会で活躍されている技術者の方々からいくつか鋭い質問をいただき、期待の大きさを実感しました。「DRは未来の消費電力をコントロールするための手法」とおっしゃっていただいたこともあります。学生の研究であっても、社会で通用するレベルの内容、結果が求められていることを痛感しました。
岩瀬:私が印象に残っているのは、初めてスマートメータのデータを目にしたときのことです。膨大なデータがただ並んでいるだけで、どこから手をつけていいかわからず、戸惑ったのを覚えています。その後、先輩にデータの見方や加工方法などを教わり、研究をスタートさせることができました。
学生一人ひとりに恵まれた研究環境
では研究環境について伺いたいと思います。なんといっても新しい研究室ということが一番の特徴ですね。
中江:今年で3年目の研究室となり、先ほども言ったように初代メンバーの1人が私です。先輩がいないため手探りで進めなければならないという苦労はあったものの、その分、いい意味での自由さは魅力です。
マイペースの研究活動が基本ですね。
中江:ええ。その雰囲気は、後輩が入ってきても変わっていないと思います。
部屋もずいぶんとゆったりしています。
岩瀬:広々として快適な環境です。椅子も座り心地がいいものを使わせてもらっています。机もかなり広いのですが、資料や書籍を広げながら研究することが多いので、とても助かっています。

新しい研究室のため、モノも少なく、スッキリとしています。
中江:面積が広いだけでなく、モノが少ないので、なおさら空間的なゆとりを感じるのだと思います。なにしろ研究ではシミュレーションがメインですので、基本的にはPC前での作業が中心なんです。
モニターは2台お使いですね。
吉田:全員2台ずつモニターを使っています。実験機器が不要な分、PCもかなり高性能なマシンを使っています。
中江:私のモニターは3台あります。データ処理で1台、その間にデータの確認をするのに1台、さらに確認したデータをWordでレポートにまとめるために1台という使い方ですね。
こちらの研究室のほか、ミーティング用の部屋もあります。
中江:この部屋では週に1回、同じテーマを研究している学生と共に、先生をまじえてミーティングを行っています。研究内容の共有や議論、進捗状況の報告などが行われ、今後の方針や次週までの課題を決めています。

別室のミーティングルームでは、研究の発表などが行われます。
吉田:もちろん何かわからないことがあれば、ミーティング以外でもそのつど先生に相談できます。
静かで快適な環境の中、研究に専念
普段の研究室はかなり静かな印象ですね。
岩瀬:それぞれ個人で研究テーマを持ち、しかもPCでのシミュレーションが中心ですから、研究室にはキーボードを叩く音だけが響いていることも珍しくありません。
吉田:音楽を聴きながらPCと向き合っている仲間も少なくないですよ。
中江:私は趣味が音楽鑑賞ですので、研究中もロックや電子音楽など、手当たり次第にさまざまな音楽を聴いています。ボーカルが入るとつい言葉の意味に気を取られてしまうので、歌の入っていない音楽が多いですね。
岩瀬:私は逆に人の声がざわざわしているほうが集中できるタイプなので、音楽ではなくてスマホでラジオを聴いています。芸人のトークなどが好きです。
コロナ禍ですから、研究室以外では一緒に過ごしにくいでしょうね。
中江:そうですね、時々帰りにみんなで近所のラーメン屋に寄るぐらいですね。飲み会等は自粛しています。
岩瀬:研究室の活動ではないのですが、私は大学の生協が行っている、新入生向けパソコン講座の運営委員会の仕事をしています。担当していたのはPower Pointの講座のリーダーで、この講座をきっかけに人間関係が広がるのを楽しんでいます。現在は中心メンバーから外れているのですが、時間があるときに手伝えたらと思っています。

研究中は黙々と、それ以外は和気あいあいと。オンとオフのちょうどいいバランスが魅力です。
コロナ禍でも就職活動は順調に進む
皆さん、電気工学を学んでいてよかったと思うのは、どんな点ですか。
中江:やはり電力に関する関心が高まったことですね。私は配電設備のデータの解析をしているので、普段、道を歩いていても電柱が気になってしまいます。つい見上げて、ああ、ひびが入っているな、と確認したり。
吉田:私も社会問題に対して関心が高まりました。以前はニュースを見ても自分の意見をもつことはあまりなかったのですが、電気工学を学ぶようになってからは、社会のさまざまな問題と電気工学を関連付けて考え、自分なりの意見を持つようになりました。
岩瀬:以前は電気工学と聞いても回路をつくるくらいしかイメージできなかったのですが、実際には想像以上に幅広い分野があると知りました。活躍できる分野も広くて、大学に寄せられた求人票を見ても、食品など、電気とあまり関係なさそうな業界からの求人があったことに驚きました。電気工学の技術者は、それだけさまざまな分野で活躍することが求められているのだと思います。
中江:今年はコロナ禍だったのでオンライン就活が中心でした。そのため同期の仲間の就活の状況がよくわからなかったのですが、だいたいみんな就職先が決まったようです。こんな経済状況でも電気工学の技術者への求人ニーズは高いんですね。アドバンテージの高さを改めて感じました。
吉田:岐阜大学では4月から6月にかけて登校できませんでした。しかしその間、先輩たちがしっかりと就職を決めていたのにはびっくりしました。中江さんも就活をしているそぶりなんて少しも感じさせなかったのに、さすがです。
では最後に、将来の夢を聞かせてください。
中江:私はIT系の企業にSEとして入社することが決まりました。社会人になったら1人の技術者として、日常生活を支えるシステムを開発して社会を支えたいと思います。公共系のシステムには特に興味があります。
吉田:私はインフラ関係の仕事に関心があります。具体的には電力会社等で、社会を支える仕事がしたいですね。できれば地元で活躍できればと思っています。
岩瀬:私は大学院への進学を考えているので、就職はまだ先のことです。現時点では分野を限定せず、幅広い業界で自分の可能性を見ていきたいと考えています。これからビッグデータはさまざまな業界で活用が進むと思うので、研究で得た知見を活かす場は広いと考えています。さまざまな業界、さまざまな企業を検討して、広い視野で社会に貢献したいと思います。
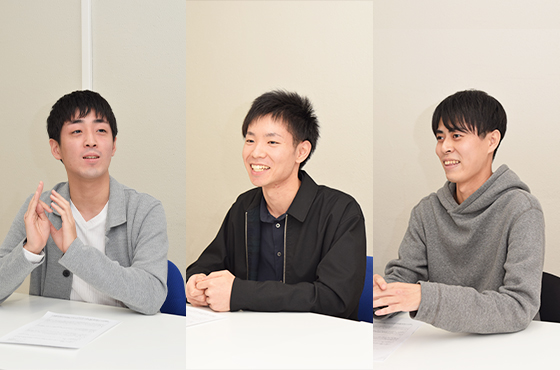
皆さん、今日はどうもありがとうございました。
※インタビューは十分な距離を取り、ソーシャルディスタンスに配慮して行いました。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。
バックナンバー
バックナンバーを絞り込む
研究キーワードから探す
大学の所在地から探す
サイト更新情報をお届け
「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。