電気の施設訪問レポート vol.8

電源開発・北本連系設備を訪問しました

2011年11月、パワーアカデミー事務局は、北海道・本州間電力連系設備(北本連系設備)の函館交直変換所を訪問しました。北本連系設備は、日本初の高電圧直流送電線という技術で、1979年に完成した北海道と本州間の電力連系設備です。これにより、日本の電力系統は、北海道から九州までひとつになりました(1993年に増設して、現在の60万kWの送電容量になりました)。本レポートでは、北本連系設備の概要と直流送電のメリット、そして見学させて頂いた函館交直変換所を紹介します。
北本連系設備がつくられた理由
日本の国土は、沖縄などの諸島地域をのぞくと、北海道、本州、四国、九州に分かれます。また、電力系統の周波数も東西で50Hzと60Hzの2系統に分かれています。この間は、設備容量に限界はありますが、直流技術を用いた周波数変換設備で連系されています。
このように分断されている日本の電力系統は、経済性や安定供給を向上させるため、相互に連系が進められてきました。特に、北海道から本州間は、津軽海峡に隔てられており、長きにわたって技術的、経済的に連系が困難でした。しかし1979年、日本初の高電圧直流送電線という技術により、ついに北海道から本州間の連系が実現。日本の電力系統は、北海道も含めて九州まで電力系統がつながりました。
連系の効果
北本連系設備により北海道と本州の電力系統が連系されたことで、次のような効果があります。
- 地域間の電力相互融通により、供給予備力(※)が節減される。
- 発電コストの低い発電所の利用率が向上し、経済的な運用が期待できる。
- 周波数変動の影響を瞬時に軽減できるので、電気の品質が向上する。
- 異常渇水時、電力需要の急増、災害発生時などに他の地域から任意の電力融通が受けられる。
(※)供給予備力
供給予備力とは、電力機器・電力設備において事故、渇水、需要の変動などの不足の事態が発生しても、想定される需要以上の供給力を持つことが必要であり、この時の供給力から需要を差し引いたものです。
東日本大震災での活躍
昨年の東日本大震災では、北本連系設備は、電力不足に陥った東北、関東地域に北海道から60万kWの電気を送り続けました(2011年10月からは30万kWの電気を送電)。
震災発生から2日後の3月13日午前2時45分。北本連系設備は、本州側に送電を開始。約半年間、60万kWのフル稼働を続けました。半年間の累積通過電力量は約23億kW時にものぼります。
高電圧直流送電線(直流送電)のメリット
通常、送電は交流ですが、北本連系設備は直流送電です。この直流送電によって、様々なメリットが発生します。
- 電線の数が少なくてすみ、建設費が安価なので長距離送電では有利になります。また、ケ―ブル区間を含む場合は、さらに経済性が高くなります。
送電線(2回線)の場合
- <交流>電線6本(交流は三相なので1回線3本、これが2回線分)
- <直流>電線3本(北本連系線の場合、本線が2本と帰線が1本*)
*2本の本線に1本の帰線がつながる。2本の本線はそれぞれ電流が逆向きなため、帰線の電流は打ち消されて、小さな電流となる。
- 送電距離が長くなると送電能力が低下する安定度の問題がなくなり、長距離送電に適しています。世界を見渡すと直流送電を適用している国も多く、中国などでは1000km、2000kmにも及ぶ長距離直流送電が実現しています。
- 異なった周波数の系統間の連系ができます(佐久間数周波数変換所など)
※詳細は身近な電気工学「第10回 周波数変換所の謎、徹底解剖!」
- 送電電力を高速に制御できるので、運用制御が容易です。
- 系統の周波数調整に利用できます。
北本連系設備の仕組み
北本連系設備は、海底ケーブルと架空送電線をあわせた直流送電区間の総延長は167km。
最大60万kWの電力が海面下約300mの海底を経由して送電されます。
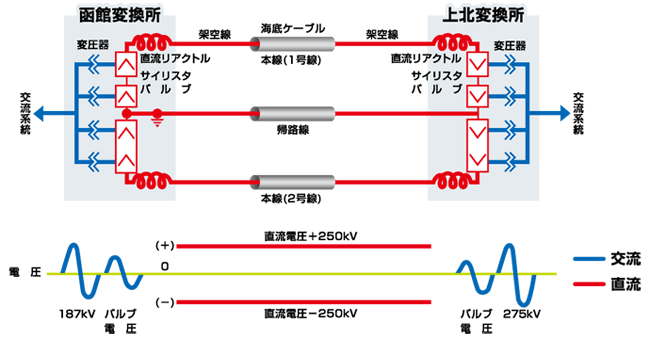
北本連系設備の構成は大きく分けて、交直変換所、海底ケーブル、架空送電線の3つとなります。また、交直変換所と隣接変電所の間の交流架空送電線も設けられています。
交直変換所

交直変換所は、北本直流送電線の両端(北海道側と本州側)に設置され、交流を直流に、直流を交流に変換する役割を果たします。
海底ケーブル
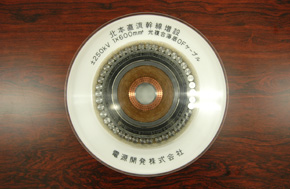
光ファイバ複合海底OFケーブル(サンプル)
海底ケーブルは、津軽海峡の海底を函館から下北半島までの約43kmにわたり敷設されています。直流本線にはOFケーブルが採用されており、ケーブルに絶縁油を加圧・充填して電気絶縁を確保しています。また、変換器の制御保護信号用の光ファイバが内蔵されています。
架空送電線

函館交直変換所から見た、直流架空送電線
架空送電線は直流区間と交流区間を持っています。直流架空送電線は海底ケーブルの上陸地点から両端の交直変換所まで設けられており、北海道側は約27km、本州側は約97kmの長さになります。交流架空送電線は交直変換所から接続する交流系統の変電設備まで設けられており、北海道側は0.8km、本州側は2.8kmの長さです。
北本連系設備の主要施設
北本連系設備の主要設備を案内していただきました。
サイリスタバルブ
サイリスタバルブとは交流を直流に、または直流を交流に変換するスイッチの役割を果たす、交直変換設備の心臓部といえる設備です。「サイリスタ」という半導体を用いて、電気の流れを調節します。
サイリスタバルブでは、直径約10cmの「サイリスタ素子」をモジュール化(引き出し状のユニットに数個ずつ直列にして内蔵)して、組み上げています。

サイリスタバルブ

サイリスタモジュール
交流フィルタ

サイリスタバルブでの交直変換により発生する、高調波電流(交流側)を除去します。
直流フィルタ

サイリスタバルブでの交直変換により発生する、高調波電圧(直流側)を除去します。
制御保護装置

制御保護装置は、融通電力の制御や、周波数などの各種調整などを行う装置です。
マイクロ波無線鉄塔・パラボラアンテナ
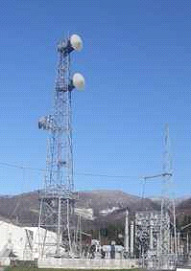
制御保護や運転保守に必要な大量の信号・情報の伝送を行う、電力保安用通信設備の一部です。
編集後記
震災の影響で、電力不足が続く中、電力連系設備の役割はますます大きくなっています。電力連系設備は、電気工学の知識や技術が大きなウェイトを占める設備。今後の能力向上のためには、電気工学のさらなる発展が欠かせないと改めて実感しました。