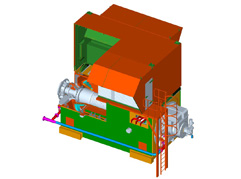「電気はミステリー」と思ったのがきっかけです
電気工学を志望された理由を教えてください。
仙波:小学生の頃から、ラジオやラジコンを作るのが好きでしたね。特にラジコンは、速度を上げるためにモーターを自作して改造していました。これで、電気にだんだん興味がわいてきました。その後、パソコンが出回って、小学生なりにプログラミングを見よう見まねでやっていました。
小学生でパソコンをいじっていたのですか。
仙波:はい。プログラムでゲームみたいなものをつくっていました。それで、電気の世界は非常に面白いなと思いましたね。当時はまだ、ITの時代ではなかったので、PCも含めて電気という認識でした。
具体的に、大学へ進まれるときに、機械工学や情報工学などもありますが、その中で電気工学へ進んだのは今おっしゃった理由が大きいのでしょうか。
仙波:そうですね。例えばラジコンならば、機械に興味があれば、シャフトやサスペンションなどに注目したと思います。しかし、私の場合はバッテリーの寿命をどう延ばそうか、モーターの出力をどう上げたらいいのかなど、そういう方面に興味がありましたので、機械よりも電気でした。「目に見えないミステリー」とでも言うのでしょうか。
それから大学院へ進まれるわけですが、大崎研究室に進まれた理由を教えてください。
仙波:東京大学工学部は、学部3年(当時)のときに専門学科へ振り分けられます。そこで、私は電気の中で強電(エネルギーとしての電気利用)分野へ進みました。大崎研究室は、強電系の中でも電力機器を扱っていて、今後も必要とされる学問だと思って選びました。また、漠然と電力関係に進みたいという希望もありましたね。
超電導応用機器の研究で、世界を駆け抜けた学生時代
大崎研究室ではどのような研究をされていましたか。
仙波:高温超電導バルク材による磁気浮上に関する研究です。高温超電導バルクとは、高温超電導材のかたまりのことで、ここに磁束を加える(励磁する)と強力な磁石になります。それを利用して、機器の浮上を試みました。
それは、リニアモーターカーの磁気浮上の原理とは違うものなのですか。
仙波:若干違いますね。リニアモーターカーは、超電導コイルに常に電流を流すことによって、浮上させます。この研究も原理は同じなのですが、一回だけ磁束をかけ、強い磁力を保持することによって、重い物を浮かせる研究をしていました。
実際に浮上できましたか。
仙波:できましたが、浮かせて終わりということではありません。単純に浮かすだけではなくて、浮かせた後にどのように制御するのかというところまでが研究範囲でした。また、超電導バルク材は、低温で管理しなければならないので、扱うのが大変だった思い出があります。
では、研究に関連して印象に残っているエピソードを教えてください。
仙波:一番面白かったのは、修士1年生のときに海外へ論文投稿したことです。学会発表で、アメリカのシアトルやMIT(マサチューセッツ工科大学)でプレゼンをしました。英語の壁にぶちあたり、なかなかうまくいかなくて悔しい思いをしたことをよく覚えています。MITでは、超電導の第一人者である日本人研究者のお話しも聞けました。MITにはその時に感銘を受け、社会人になってから留学しました。
素晴らしい経験ですね。
仙波:あとは、同じ内容を米国の交通省に興味をもたれて、説明したことも印象に残っています。私と先輩の2人で、超電導リニアモーターカーなどについてプレゼンしました。こちらはふたり、向こうは4人ぐらいでしたので、非常に緊張しました。しかも、教授ではなく役所の方へ英語でプレゼンするという経験は、社会の荒波に揉まれた感じでした。
大崎研究室のことで思い出に残っていることがあれば教えてください。
仙波:研究室は全部で15人ぐらい在籍していたのですが、そのうち2人が日立の企業内学校の生徒社員でした。彼らの年齢は私と同じくらいでしたが、研究に対する姿勢が我々と全く違い、良い刺激を受けました。つまり、社会人と学生の熱意の差というものを感じました。私が日立製作所の入社を志望した理由の一つにもなっています。また、イギリス人やブラジル人、アメリカ人、中国人なども在籍していて、国際色豊かだったことが印象的でした。研究室内では、英語に接する機会はあまりなかったですが(笑)。
最大効率の発電機をつくる、ミッション
日立製作所に入社された理由を教えてください。
仙波:日立製作所は総合電機メーカーです。電力・産業システム以外にも、情報通信システム、電子デバイス、デジタルメディア・民生機器、高機能材料、物流、金融サービスなど多岐に渡る分野を手掛けています。更にグローバルな企業でもあります。私は発電機の開発を希望していたのですが、その他のことにも携われる可能性がある企業だと考えて入社を志望しました。
なるほど。総合電機メーカーならではの志望理由ですね。
仙波:でも正直に言いますと、入社した一番の理由はここが日立市だったからです(笑)。私の趣味は釣りで、入社前に2、3回来たことがあるのですが、事業所のすぐ近くに海がありました。それで、お昼休みや退勤後に釣りができるかなと思ったのです。実際は、全くできませんでしたが(笑)。

日立駅・駅前広場に展示されている、発電所用の大型タービン動翼のモニュメント
(笑)。それでは、現在のお仕事を教えてください。
仙波:私は入社以来、主に火力及び原子力発電所向けの大型タービン発電機の設計をしています。タービン発電機とは、タービンによって駆動される発電機のことで、タービンの機械エネルギーを電気エネルギーに変える機器です。プロジェクトの期間は、火力向けは2年ぐらい、原子力向けは、許認可などを入れると10年ぐらいかかります。設計業務に従事していた頃は、だいたい5つぐらいのプロジェクトを掛け持ちしていました。
具体的に設計というのはどのようなお仕事ですか。
仙波:設計といっても、常に机の前に座っているわけではなくて、設計自体に費やす時間は業務全体の半分以下です。設計以外にも、お客様にプレゼンテーションをしたり、値段を決めたり、部材の調達指示などを行います。世界中のお客様を相手に、いろいろな国にも出向きます。私の場合は、アメリカ、カナダを中心に、中国、イギリス、インドなどへ行きました。他には発電所全体のPRなども行っています。
それは幅広いですね。これまでお仕事をされていて、印象に残っているエピソードを教えていただけますか。
仙波:色々ありますが、最近だと「最大効率の発電機を作る」仕事がありました。その発電機は、アラスカから灼熱の砂漠まで、どこでも使用されるものです。従って、何百台も売るので一つ間違うと大変なことになってしまいます。こうしたミスが許されない状況の中で、発電機の効率を競合他社よりも高くするような難しい設計をしなければいけないミッションです。
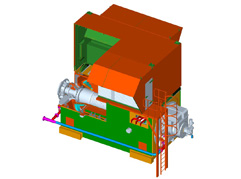
仙波さんが携わった最大効率の発電機
最大効率の発電機とはどのぐらいなのですか。
仙波:私が設計した空気冷却方式の発電機の効率というのは、おおよそ98%から99%ぐらいです。既に十分に高効率なもので、私が取り組んだのは、その効率をたった0.1%上げるという程度のものです。
たった0.1%ですか!
仙波:そうです。実は、この0.1%というのが、お客様の運用コストにおいて、年間でみると相当額効いてくるのです。
なるほど。
仙波:問題は、その0.1%の効率を上げて、なおかつ値段を安くすることです。他社とのせめぎ合いは大変なもので、2年程度かかりっきりで設計しました。また、資材を安く調達するため北米を中心に海外へも出向き、日立の品質基準をクリアするために調達先の方々と悪戦苦闘してつくりあげました。この仕事は「技術の日立」の魂を見せられたかなと自負しています。


日立の火力・原子力用タービン発電機
電気工学はモノづくりにおいて総合的な視点を養える
学生時代に学んだ電気工学は、今のお仕事にどのように活かされていますか。
仙波:正直に言いますと、設計の中で電気工学の比率は非常に少ないです。ただ、問題に直面したときに、やったことあるなぁ、と、文献などを簡単に探せたり、解決のヒントを得たり、教授や同級生などの人脈を活かしたりはしています。
一般的なイメージですと、出身学科が電気工学で、発電機の仕事に携わっておられるので直結していると思ったのですが。
仙波:発電機は、一応、電気屋さんというカテゴリーには入ると思いますが、実際は、機械工学や材料力学、破壊力学、流体力学など、総合的に学問を駆使しないと設計できないのです。
なるほど。
仙波:入社後、そのギャップに戸惑いました。私たちが学んだ電気工学というのは、発電機の世界では一部に過ぎないのです。ただし、電気の世界では、0.00・・・オームから何百万オームまで、小さいものから大きいものまで、ひとりで全部扱います。一方、他の世界では、例えば0.00・・・トンから何百万トンまで、ひとりの人では扱いづらいです。そういう意味で、電気屋さんは、小さいものか大きいものまで扱える総合的な視点を持っていると思います。
地球上で電気を欲しがっている人がたくさんいる
いま振り返って電気工学を学んでよかったなと思うことを教えてください。
仙波:私は、世界中の人が電気を欲しがっていると思います。衛星から夜の地球を撮影すると、灯りの点いている所が明るく見えます。人口密度が多いところはたくさん光っていますが、まだまだ光がないところはたくさんありますね。
世界を見ると、電気が足りないところはまだまだあると。
仙波:そういう人たちに、この仕事を通して電気という便利なものを提供できることは、良かったなと思います。現地の人からもそれで喜んでいただければ非常にやりがいがあります。
最近の仕事の中で特にやりがいを感じたものは、どのようなものですか。
仙波:最近では、韓国の商用原子炉第一号機ですね。韓国で一番古い他社製の原子力発電所で発電機が古くなったので、それだけを交換するというプロジェクトがありました。プロジェクトは成功して、短納期で高性能な製品だと喜ばれました。韓国の場合、原子力発電所の稼働率が日本に比べて非常に高いので、短納期に非常なまでの比重が置かれていました。結果として、韓国の電力事情を支えているという実感ができたのは嬉しかったですね。
電気は、今、追い風が吹いている
最後に、これから電気工学を学ぼうとする学生へのアドバイスをいただけたらと思います。
仙波:私が入社するときもそうでしたが、近年、電気工学は人気が乏しいと聞いています。なぜ魅力がないのかを考えると、成熟産業(学問)だと思っている人がかなり多いのが理由ではないかと思っています。
要するに、電気はもうどこにでもあるし、使える、と。
仙波:そうです。これからも同じものを同じ技術で作っていけばいい、新たに挑戦することはないと考えている人が多いと思います。私も入社するときに「これから新たにやることはあるのですか」と当時の面接官に聞いたことを覚えています。
そうですか。
仙波:実際にはやることはたくさんあって、世界中の電気関係の人たちとしのぎを削り、良い物をつくるために努力をしています。特に今は、自動車や発電所、鉄道などのインフラが、機械そのものから電気の分野へ付加価値が移行しているように思えます。これから追い風だと思っています。
今、電気はすごくチャンスがある分野ということですね。
仙波:はい。今が一番いいチャンスだと私は見ています。電気の需要が広まることによって、世界中の人がハッピーになって、インフラが整って生活レベルが上がる。そうすると、生活が豊かになって紛争が少なくなることだってあり得ると私は考えています。また、電気はCO2排出削減など、いろいろな地球環境に貢献ができるキーテクノロジーです。非常にやりがいのある分野だと私は思っています。
日立製作所は、まさしくその一端を担っていますね。
仙波:そうですね。日立は、今、社会インフラに力を入れることが会社の方針となっています。ですから、電気を使ったビジネスを拡大しています。地球全体の環境やエネルギーを支えるグローバルなメーカーで仕事ができることは、大きな誇りだと私自身も考えています。
本日は、電気に対しての熱い想いを存分に語っていただき、大変感銘を受けました。どうもありがとうございました。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。