vol.43 株式会社日立製作所

社会人インタビュー vol.43
電力インフラを支える仕事を通じて、環境保護などの社会貢献を続けていきたい。
株式会社日立製作所
宮原 秀幸(みやはら ひでゆき)さん
「世の中に貢献できる仕事がしたい」という志で電気工学の道に進んだ宮原さん。学生時代に取り組んだ環境負荷の小さい絶縁媒体の研究成果を、現在の変圧器の設計・開発という業務にも反映させるなど、社会貢献と環境保護というテーマを貫いてこられました。今後もその歩みを続け、電力インフラの様々な課題を解決できる人材を目指したいとお考えです。
プロフィール
- 2005年3月
- 東京電機大学 工学部 電気工学科 卒業
- 2007年3月
- 東京電機大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 修士課程修了
- 2007年4月
- 株式会社日本AEパワーシステムズ(日立製作所、富士電機、明電舎の合弁会社)入社
- 2012年4月
- 同社合弁解消による事業継承に伴い、日立製作所に転籍
- 2019年7月
- エネルギービジネスユニット エネルギー生産統括本部 送変電生産本部 変圧器設計部 中形変圧器設計グループ
※2019年7月現在。文章中の敬称は略させていただきました。
リンゴに落雷させる実験を見て研究者の道へ
宮原さんが電気工学を学ぼうと思われた動機を教えてください。
宮原:もともと理系科目が得意で、中学時代にはトランジスタラジオを作るなど、ものづくりに興味がありました。電気工学科なら電気、電子、情報、数学、物理、化学などを幅広く学べ、さらには文系の授業もあるということから、様々な学びを通じて将来に向けて興味を持てる何かが見つかるのではと考えました。
具体的にこんな仕事がしたいというイメージはお持ちでしたか。
宮原:いいえ、将来に対しては、世の中に貢献できる仕事がしたいという漠然とした想いでしたね。
学生時代はパワーシステム研究室に所属されていたそうですね。

宮原:ええ。大学3年生の時に研究室見学を行った際、ある研究室の実験を見て大変驚きました。インパルス発生装置で雷を発生させてリンゴに落雷させるというものでした。それまで電気というのは数式や検針でしか存在が確かめられないものだと思っていたのに、このとき、初めて電気を目にすることができたのです。そのインパクトは大きく、自分も高電圧工学を学びたいと思いました。その研究室が、送変電機器の基礎研究をしていたパワーシステム研究室だったのです。
環境負荷の少ない代替絶縁媒体の研究に取り組む
パワーシステム研究室ではどんな研究に取り組まれましたか。
宮原:研究室では主に電力機器の開閉装置や変圧器に使われる絶縁媒体の研究を行っており、環境負荷の少ない、新しい代替絶縁媒体の研究に取り組んでいました。その中で私は、シリコーン液(※1)を代替絶縁媒体として用いることを目的に、絶縁特性の評価を行いました。
(※1)合成高分子化合物の無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、酸化安定性に優れている。
非常に社会貢献性の高い研究ですね。
宮原:はい。液体の絶縁媒体として通常使われる絶縁油は土壌汚染や資源枯渇の懸念があり、また、気体の絶縁媒体として通常使われるSF6(六フッ化硫黄ガス)は地球温暖化への影響が心配されています。その点、シリコーン液は環境や動植物に無害で、かつ防災性に優れ、地下資源を用いない持続可能な絶縁媒体として注目されていました。電力インフラを支える送変電機器も環境問題や資源問題を抱えており、私はこの研究を通じてそうした問題の解決に貢献できることに喜びを感じていました。
研究室での思い出を教えてください。
宮原:学会発表でインドネシアへ10日間の旅をしたことが思い出に残っています。私にとって初めての海外でした。仲間と一緒にバリ島を観光したことは、いい思い出です。学会発表そのものは大変緊張し、慣れない英語にも苦労しました。それでも海外の多くの研究者から大変好評でした。
どんな点が評価されましたか。

宮原:シリコーン液の絶縁試験のデータ取得には非常に時間がかかり、1つのデータを取るために20時間も必要で、それを何回も繰り返す必要がありました。そのため研究室に泊まり込む毎日だったのですが、こんなに時間のかかるデータをまとめ上げた、という点が特に評価されたと思います。苦労した研究だっただけに、私も大きな達成感を得ることができました。
電気工学の専門家として、トータルなものづくりにも携わる
就職に際してはどのような思いをお持ちでしたか。
宮原:学生時代の研究成果を踏まえ、電力インフラを支える仕事に従事したいという想いがありました。同時に、子供の頃からものづくりが好きでしたから、電気工学の知識を活かしてものづくりに取り組みたいとも考えました。
現在のお仕事内容について教えてください。
宮原:主に100MVA以下の中容量の変圧器の設計・開発を担当しています。民間企業の工場や鉄道会社などで使用されるものが多いですね。変圧器の性能を決める電気設計を主に担当していますが、お客様の要望をヒアリングして仕様を決めたり提案したりする段階から設計作業、工場の製造の立ち会い、出荷前試験の立ち会い、現場での据え付けと、最初から最後まで携わることができています。
ものづくりに携わっているという手応えは大きいでしょうね。
宮原:まさにものづくりにトータルに関わることができているという達成感があります。これはとても大きなやりがいです。また、自分が設計した変圧器が工場や鉄道で今も稼働しているわけですから、社会に不可欠なものづくりができているという実感もあります。
変圧器そのものの進化にも貢献できるのではないでしょうか。

宮原さんが設計・開発を担当した変圧器は中容量のものが多く、工場や鉄道などの安定稼働を支えています。
宮原:幸い、入社して1年後にはシリコーン液を用いた変圧器の開発にもチャレンジできました。変圧器そのものは古くからある機器ですが、絶縁媒体や材料など、まだまだ改良の余地は多くあります。変圧器をさらに進化させていくことは、私にとって大きなテーマです。
波の上に浮かぶ発電システムの実証研究事業に参画
これまでで一番印象に残っているのはどんな業務でしたか。
宮原:2013年に福島県沖の海上で運転を開始した浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業において、その変圧器の設計に携わったことです。国内の有力企業が多数参画して進められた実証研究事業で、世界初の試みということもあって、私にとっても大変に誇らしい経験となりました。
浮体式ということは、海の上に浮かんでいる発電システムということですか。
宮原:その通りです。そのため、地上の発電システムと違って常に波の上で揺られており、そのような環境でどのような検証をすれば性能を保証できるか、その検証は実施可能かなど、まさに前例のない中での手探りの検証となりました。また、この変圧器にはシリコーン液を用いたのですが、海上においてもシリコーン液の環境への無害性や防災性などは担保されるか、検討を繰り返しました。
学生時代の研究の経験を活かすことができたのですね。
宮原:ええ、たいへん有り難い機会だと思いました。最終的には実際に変圧器が据え付けられた現場にも立ち会うことができ、大きな達成感を得ることができました。製品技術を学会で発表した際は、学生時代の学会発表の経験も活かすことができ、そうしたことも含めて、本当に有意義なプロジェクトでしたね。
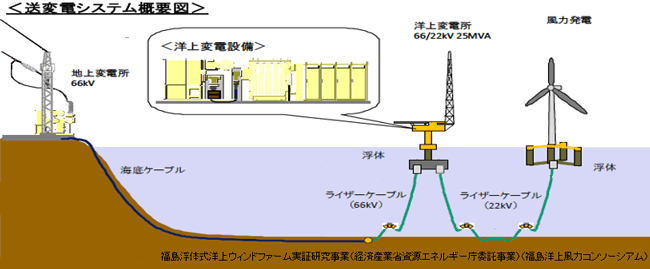

宮原さんが参画した浮体式洋上風力発電システムの実証実験プロジェクト。写真は変圧器の傾き試験の様子。浮体の上に設置するため、揺れへの十分な対策が求められました。
“目に見えない”電気を学ぶことで“目に見える”他の分野の学びが有利に
学生時代に学んだ知識は、仕事の上でどのように活きていますか。
宮原:学生時代の勉強が毎日の仕事に不可欠なのはもちろんですが、むしろ社会人になってからも日々勉強が必要というのが実感です。今の担当分野だけならば電気工学の専門知識だけで十分かもしれませんが、業務を進めていく上では内外の他の専門家と関わらなくてはなりません。そのため電気工学に限らず、幅広い分野の知識が必要となります。情報工学や半導体、電子材料、化学、機械など、私も様々な分野の学びを続けています。
なるほど、電気工学の知識を核として、周辺の専門知識を増やしていくというイメージですね。
宮原:ええ。専門以外の話題になったときも“これは教科書の何ページに出ていた”という具合にパッとイメージの浮かぶことが大切だと思います。それに、電気という目に見えないものを苦労して学んできたことで、物理や機械などの目に見える分野を学ぶのには、さほど苦労しないというのが実感です。その意味で学生時代に電気工学をじっくり学んでおくことは、就職してからの勉強の力になると感じます。
将来の目標を教えてください。
宮原:やはり昔からずっと大切にしてきた“社会に貢献できる仕事をしたい”という志は持ち続けたいと思います。その上で、お客様の課題解決を通じて、インフラを支える仕事に携わっていきたいと考えています。その舞台がグローバルなものであるかもしれません。お客様の課題が海外にあるならば、そこまで飛んでいって解決に取り組みたいですね。IoTにより変電所の無人化ニーズも高まっていますから、その実現にもチャレンジしたいと思います。
最後に学生の皆さんにメッセージをお願いします。

宮原:社会に出ると自分の専門以外の専門家の人々とも関わることが多くなると申し上げましたが、その際にはヒューマンスキルも大切になります。リーダーシップに自信があるならまとめ役として、協調性があるなら人のサポート役として、といった具合に自分ならではの持ち味を活かして活躍して欲しいと思います。そのためにも学生時代には様々な経験を重ねて、ヒューマンスキルを磨いてください。
宮原さんのさらなる社会貢献に期待したいと思います。本日はありがとうございました。
※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。
バックナンバーを絞り込む
研究キーワードから探す
業種別で見る
サイト更新情報をお届け
「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。